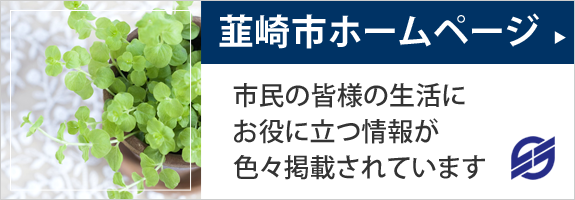おしえてドクター
韮崎市が発行する「広報にらさき」の情報コーナー「おしえてドクター」で取り扱ったものを掲載しています。
皆様の病気・症状への不安や悩みを、当院の医師がお答えします!
2025年
| 2月 | |
| 1月 |
2024年
| 12月 | |
| 11月 | |
| 10月 | |
| 9月 | |
| 8月 | |
| 7月 | |
| 6月 | |
| 5月 | |
| 4月 | |
| 3月 | |
| 2月 | |
| 1月 |
2023年
| 12月 | |
| 11月 | |
| 10月 | |
| 9月 | |
| 8月 | |
| 7月 | |
| 6月 | |
| 5月 | |
| 4月 | |
| 3月 | |
| 2月 | 70歳代女性。コロナ禍のため運動不足の状態で、半年前より両側の下腿がむくみ、最近では右下腿皮膚の一部が痒くただれてきています。 |
| 1月 |
2022年
| 12月 | |
| 11月 | |
| 10月 | |
| 9月 | |
| 8月 | |
| 7月 | |
| 6月 | |
| 5月 | |
| 3月 | |
| 2月 | |
| 1月 |
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2025年2月号

皮膚の発疹がある人に関節痛や腰背部痛が出ることがあると聞きました、どんな病気なのでしょうか?

乾癬(かんせん)という皮膚科の病気に、関節痛や腱の付着部の炎症を伴う病態(乾癬性関節炎)が起こることがあります。
リウマチ科 小山 賢介
乾癬という皮膚科の病気に、関節痛や腱の付着部の炎症を伴う病態(乾癬性関節炎)が起こることがあります。腱の付着部は脊椎にもあるため、腰痛や背部痛などの症状を伴うことがあります。乾癬は、髪の毛の生え際、臀部など自分では気づかない場所に出ることもあり、爪のみに症状が出ることもあります。
整形外科に受診する際、皮膚の症状を問診されることは少なく、皮膚科に受診する際、関節痛や腰背部痛の問診をされることは少ないのが現状であり、見逃されている患者さんも多く存在します。
乾癬性関節炎は、生活習慣病との関連も指摘され、日本人にも増えてきている病気です。強直性脊椎炎、炎症性腸疾患などまれな病気とも鑑別が必要になることもありますので、専門科で一度相談してみるのことをお勧めします。
2025年1月号

2型糖尿病のため通院しています。外来で渡される、生活習慣病療養計画書の「HbA1cの目標」とは正常値と違うのですか。

病状や生活環境から正常値を維持するのが難しい方のための、実現可能な目標のことです。
内科 保阪 大也
糖尿病、高血圧、脂質異常症を主とする生活習慣病の患者さんが増加しているため、厚生労働省はそれを抑える対策の一環として、患者さん個々に応じた療養計画書を作成してお渡しすることを勧めています。
HbA1cの正常値は5.8%以下で、それを維持することが理想です。しかし、病状や生活環境からそれが困難な方には、実現可能な目標を立ててがんばっていきましょう、という意味です。目標とするHbA1cは以下を目安として病状に合わせて決めます。
6.0%未満:血糖正常化を目指す際の目標
7.0%未満:合併症予防のための目標
8.0%未満:治療強化が困難な際の目標
65歳以上の方は日常生活自立度や認知機能の程度、低血糖の危険を考慮してプラス0.5~1%
できるところから少しずつ目標を達成していきましょう。
2024年12月号

内科で3週間程入院し、ほとんどベッド上で動かなかったのに膝の痛みが強くなりました。どうしてですか?

軟骨は、関節液から栄養をもらっています。関節を動かすことによって関節液を隅々まで運んでいるため、ほとんど動かさないでいると軟骨の修復が十分できず痛みの原因となります。
整形外科 小川 知周
骨も軟骨も壊されては修復されを繰り返しています。修復されるには酸素と栄養が必要です。骨には神経や血管があるのでそこから運ばれてきますが、軟骨には神経も血管も存在しません。
では、どうやって栄養をもらっているのでしょう?実は、軟骨は関節液から栄養をもらっています。正常な関節は、ごくわずかな関節液しかありません。その少ない関節液を、関節を動かすことによって隅々まで運んでいるのです。そのためほとんど動かさないでいると軟骨の修復が十分できず痛みの原因となります。また動かさないことで自分の体が関節液が足りないと認識し、滑膜という組織で関節液を過剰に作ってしまい関節に水が貯まり、痛みや発熱の原因となります。
病気や怪我であまり動けない人でも動かせるところは動かして関節痛の予防をしていきましょう。
2024年11月号

30歳代女性、検診の乳腺エコーで1㎝程の腫瘤を指摘され、「乳腺線維腺腫」と診断されました。どのような病気でしょうか。

良性のしこりで、自然消退することもある腫瘤です。エコーやマンモグラフィにて、癌との区別は比較的容易に行うことが可能です。
外科 鈴木 修
20~30歳代の女性に多く発症する良性のしこりで、ゆっくり発育し、2~3㎝以上には大きくならず、自然消退することがある腫瘤です。エコーやマンモグラフィにて境界が明瞭で平滑な扁平型の腫瘤所見を示し、粗大な石灰化を認め、癌との区別は比較的容易に行うことが可能です。判断に迷うような際には針を刺して細胞の一部を採取し、顕微鏡検査にて診断を行います。
顕微鏡検査にて線維腺腫と診断されても、葉状腫瘍と呼ばれる良性と悪性の中間的性質をもつ腫瘍の可能性もあり、腫瘍径が3㎝を超えて増大するようであれば、葉状腫瘍を疑い切除することが勧められます。
月に一度は自身で乳房の触診を行い、6~12ヵ月の間隔で定期的な検査を受けることが望まれます。
2024年10月号

糖尿病になると目が悪くなるのですか?

目の網膜は特に糖尿病の影響が出やすい臓器です。糖尿病がある方は目の症状がなくても、少なくとも年に一度は眼科を受診して定期チェックを受けましょう。
眼科 葛西 友香
糖尿病は、インスリンというホルモンの不足や作用低下が原因で血糖値が高くなる病気です。血糖値が高いと、全身の血管が傷ついたり詰まったりして様々な症状が出てきます。
目の網膜は細かい血管が集中しているため、特に糖尿病の影響が出やすい臓器です。糖尿病による網膜の変化を糖尿病網膜症といい、進行すると眼内に大出血を起こして失明することもあります。その他にも白内障が早く進行したり、タチの悪いタイプの緑内障になったり、目の中に炎症を起こしたり、目を動かす筋肉が麻痺したりとたくさんの目の病気が起こります。
糖尿病網膜症は自覚のないうちに進行するため、見えにくくなってから受診しても手遅れということもあります。糖尿病がある方は目の症状がなくても、少なくとも年に一度は眼科を受診して定期チェックを受けましょう。
2024年9月号

肛門から腸が出てきます。なかなか人に相談できないのですがこれは何という病気でしょうか?

直腸脱という病気です。お尻の病気はなかなか受診するのに勇気がいりますが、早めの受診で早めの治療を行えば、治療内容も軽く済みます。
外科 赤澤 祥弘
特に高齢の方に多いのですが、直腸脱というものです。内痔核(いわゆるいぼ痔)という病気と混同しやすいのですが別の病気です。
直腸脱は高齢の痩せた女性に多く、原因はお尻の筋肉の一部が弱くなることによって起こるといわれています。筋肉が弱ってきて、直腸を支えることができずにお尻から直腸が出てきます。女性の場合は子宮が一緒に出てくることがあります。
直腸脱の治療は手術しか方法がなく、自然治癒することはありませんので受診して頂いたほうが良いです。治療を早めに開始しないと、悪化して出てくる腸の量が増えるので早めの治療をお勧めします。
いぼ痔にしても直腸脱にしてもお尻の病気はなかなか受診するのに勇気がいりますが、ほかの病気と同じで早めの受診で早めの治療を行えば、治療内容も軽く済みます。
2024年8月号

手がしびれていて手根管症候群かもと言われました。どういった状態でどういう治療法などがあるのでしょうか?

手首にある神経が圧迫されることで起こる病気です。治療には安静にする、冷やす、固定するなどの方法がありますが、改善しない場合は手術が必要なこともあります。
整形外科 三井 康平
手根管症候群は、手首の手根管という細い通路が狭くなり、その中を通る正中神経が圧迫されることで起こる病気です。この病気は、手首を多く使う作業や長時間同じ姿勢でいることが原因となることがあります。症状としては、手や指のしびれや痛みがあり、特に親指、人差し指、中指に出やすいです。夜になると痛みやしびれが強くなることもあります。
治療には、手首を安静にし、冷やしたり固定する装具を使ったり、理学療法を受けたりする方法がありますが、症状が改善しない場合は手術が必要になることもあります。予防するためには、手首を無理に使わず、こまめに休憩を取り、手首を休ませることが大切です。
症状に困っていましたら近所の整形外科でも当院でもご相談いただけましたら幸いです。
2024年7月号

「介護医療院」とは今までの介護病床とは何が違うのでしょうか?

「介護医療院」は、長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、長期療養のための医療と日常生活の支援を一体的に提供します。
内科 池田 フミ
「介護医療院」は住まいと生活を医療がささえる新たなモデルとして創設された施設です。長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、長期療養のための医療と日常生活の支援を一体的に提供します。
令和6年4月に病院の介護病床から移行して新たに開設をされた施設も増えてきています。介護認定をうけている方で病院に入院するほどではないものの、継続的な医療管理、たとえば痰の吸引や経管栄養などを必要とし、在宅や他の介護施設で支えることが難しい方が対象となります。
在宅を目指した「自立支援」やリハビリも提供しますが、「看取り・ターミナル」を支えることも重要な役割となります。
入所をご希望される方は自治体や包括支援センターに相談してみましょう。
2024年6月号

以前から腰の痛みがあります。何でしょうか?また日常生活で気をつけることはありますか。

腰痛にも種類や原因は様々あります。健康的な体重管理、日常的な運動実施、健康的で穏やかでストレスが少ない生活を心がけましょう。
整形外科 亀山 啓吾
腰痛とは、体幹後面に存在し、第12肋骨から殿溝下縁の間にあり少なくとも1日以上継続する痛みをいいます。発症から4週間未満を急性腰痛、4週~3か月未満を亜急性腰痛、3か月以上のものを慢性腰痛といいます。原因としては重篤な基礎疾患(悪性腫瘍、感染、骨折など)、下肢の神経症状を併発する疾患、脊柱構成体の退行性病変(椎間板・追完関節変性など)があります。急性腰痛は自然軽快を示すことが多く予後は良好ですが、慢性腰痛の自然経過は急性腰痛と比べて不良といわれます。
日常生活で気をつけることですが、健康的な体重管理が腰痛予防に好ましいとされています。標準体重(BMI18.5~25.0)より低体重または肥満では腰痛発症のリスクと関連が見られます。また日常的な運動実施、健康的で穏やかでストレスが少ない生活が推奨されています。
2024年5月号

胃(大腸)カメラを受けます。かかりつけ医で処方されている血液をサラサラにする薬は休薬が必要ですか。

近年は、観察のみや1剤内服時の生検は休薬しないで行うことが増えています。出血を伴う処置が必要な際にも、内視鏡医と抗血栓薬処方医とで相談しますので、抗血栓薬の自己中止はしないようにお願いします。
院長 井上 泰輔
胃や大腸の内視鏡検査時には、悪性疾患の鑑別のために組織を採取する生検や、ポリープ切除術を行う可能性もあり、以前は出血の予防を優先して抗血栓薬を休薬することが主流でした。しかし近年は抗血栓薬を休薬すると、出血よりも重篤となりうる血栓塞栓症(脳梗塞や心筋梗塞など)のリスクが高まるため、観察のみや1剤内服時の生検は休薬しないで行うことが増えています。
出血を伴う処置が必要な際には、処置による出血の危険度、血栓塞栓症発生の危険度、抗血栓薬の種類や数によって対応が異なりますので、内視鏡医と抗血栓薬処方医とで相談し、受検者様が説明を受けて理解されることが必要となります。抗血栓薬の自己中止はしないようにお願いします。
2024年4月号

眼科で緑内障と診断されました。どんな病気なのでしょうか?

緑内障は、眼の奥にある視神経が障害され視野が狭くなる病気です。障害された視力や視野は治療によっても回復することはないため、早期発見と適正な治療が大切です。
眼科 北村 一義
緑内障は、眼の奥にある視神経が障害され視野が狭くなる病気で、治療が遅れると失明することもある怖い病気です。原因の1つに眼圧という眼球内の圧力の上昇がありますが、日本人は眼圧が正常な正常眼圧緑内障が多いです。疫学調査では40歳以上の20人に1人が緑内障で、未治療の方が多いと言われています。視野障害は比較的ゆっくりと進み、視力に影響する中心部よりもその周囲から見えなくなっていくことが多く、見え方がおかしいと気づいた時にはかなり進行していることもあります。
障害された視力や視野は治療によっても回復することはないため、早期発見と適正な治療が大切です。治療はまず眼圧を下げる効果のある点眼薬の治療を始めます。点眼薬の効果や視野障害が進む速さには個人差があり、眼科の検査でしか明確には分からないため、定期診察は必ず受けましょう。
2024年3月号

腹部外科領域で緊急手術になる疾患を教えてください。

急性虫垂炎、急性胆嚢炎、腸閉塞、消化管穿孔等があります。
外科 須貝 英光
腹部外科領域で緊急手術になる疾患は「急性腹症」と言われ、ときに緊急手術となります。当科でも年間約50例の緊急手術があり、主な疾患は以下です。
・急性虫垂炎
症状は心窩部痛→臍部痛→右下腹部痛、悪心・嘔吐を伴い、発熱あり。治療は保存的治療(抗生剤)、腹腔鏡下・開腹手術。
・急性胆嚢炎
症状は悪寒戦慄を伴う発熱、上腹部痛、黄疸。治療は絶食抗生剤投与、胆道減圧法、緊急腹腔鏡下・開腹手術。
・腸閉塞
消化管術後に多い。開腹歴がない場合鼠径ヘルニア、腫瘍が原因の場合がある。治療は絶飲食治療、症状悪化で手術を考慮する。また、血流障害がある腸閉塞は原則手術となる。
・消化管穿孔
症状は突然の激しい腹痛。上部消化管穿孔では消化性潰瘍の既往。胃、十二指腸穿孔は、発症初期なら保存的治療(薬物、絶食、胃管挿入) 、腹腔鏡下・開腹手術。小腸、大腸穿孔は、開腹手術。
その他婦人科疾患、泌尿器科疾患、腹部大動脈瘤などがあります。
2024年2月号

2型糖尿病で食事療法をしていましたが、そろそろ薬が必要と言われました。低血糖が心配です。

最近の内服薬は比較的低血糖を起こしにくくなっているので必要以上に恐れることはありません。家族や周囲の人との情報共有、低血糖前の行動の把握が大事です。
内科 保阪 大也
糖尿病治療では低血糖への対処がとても重要です。でも、最近の内服薬は比較的低血糖を起こしにくくなっているので必要以上に恐れることはありません。
しかし、血糖管理が割と良い方(HbA1c6.8%以下程度)、インスリン治療中、スルホニル尿素薬やグリニド薬内服治療中の方、高齢の方等は注意が必要です。
低血糖症状(概ね軽い順):起床時の頭痛、空腹感、無気力、だるさ、集中力低下、冷や汗、動機、ふるえ、顔面蒼白、ほてり、意識もうろう、異常な行動や言動、けいれん、昏睡
意識がしっかりしていれば、ブドウ糖10g、砂糖なら20g相当を摂取して経過によって追加し様子をみます。下線の症状の場合は救急車の要請が無難と思われます。
家族や周囲の人との情報共有(病気のことやブドウ糖の置き場所)、低血糖前の行動の把握(食事、内服、入浴、運動の程度や時間、体調等)が大事です。
2024年1月号

子供が血尿を指摘されました、どんな病気が考えられますか?

他に異常が無く自然に改善する可能性が高い血尿や、良性家族性血尿等の治療の必要が無い場合がほとんどです。経過中稀に病気と診断される事もあるため、定期検尿は続けてください。
小児科 大城 浩子
血尿は程度により顕微鏡的血尿と肉眼的血尿とに分けられます。顕微鏡的血尿は尿の色は普通で見た目では分かりません。学校検尿や3歳児検診で偶然発見されるのは、大半が顕微鏡的血尿です。発熱時や運動後にも一過性に血尿を認めることもあり、この様な方は病院で早朝尿を再検すると陰性になります。
再検でも血尿を認める場合は、血圧測定、血液検査、腹部エコー等行います。ほとんどの場合、軽度の血尿以外に異常が無く、原因不明だけど自然に改善する可能性が高い血尿、もしくは良性家族性血尿(生まれつき腎臓の血管の壁が薄く血尿が出やすい)等、特に治療や食事・運動制限の必要がない血尿です。外来で定期的に検尿を行いながら経過をみます。
しかし経過中稀に、血尿の悪化や蛋白尿の出現を認め、慢性糸球体腎炎等の治療が必要となる病気と診断される事もあるため、定期検尿は続けてください。
2023年12月号

腹部超音波検査で胆嚢ポリープを指摘されました。癌化のリスクはありますか?

胆嚢ポリープは基本的には良性のものがほとんどです。大きさ、増大傾向、ポリープの茎が幅等から、悪性の可能性が否定できない場合は手術を検討します。
内科 髙橋 英
胆嚢ポリープとは胆嚢粘膜に出来る限局した隆起病変の総称で、基本的には良性のものがほとんどです。胆嚢ポリープの中で最も多いのがコレステロールポリープ(胆汁中のコレステロールが胆嚢に付着)であり、約90%を占めています。多くは数mm以内のものが多く、多発しやすいことが特徴です。その他、腺腫、過形成ポリープ、炎症性ポリープなどがあります。
胆嚢ポリープと診断された中で精査や治療(手術)が必要になるのは、胆嚢癌の存在する可能性があるものになります。大きさが10mm以上、増大傾向、大きさに関わらず広基性病変(ポリープの茎が幅広い)や充実性低エコー所見など悪性の可能性が否定できない場合は手術を検討します。
当院では専門医や検査機器も充実し、安心して診療を受けていただける体制が整っています。お気軽にご相談ください。
2023年11月号

肩を動かすと痛みがあり、夜間にも痛みが出たりしますが、どのような疾患の可能性がありますか。

肩関節周囲炎、それに伴う肩関節拘縮、上腕二頭筋長頭腱炎、腱板断裂等があげられます。
整形外科 松木 寛之
運動時の痛みや夜間の痛みを認める主な肩関節疾患としては、肩関節周囲炎、それに伴う肩関節拘縮、上腕二頭筋長頭腱炎、腱板断裂等があげられます。
肩関節周囲炎、上腕二頭筋長頭腱炎は、肩関節の周囲の組織に炎症が起きることにより生じる疾患です。炎症後に関節包などが癒着し肩関節の動きが悪くなった状態が肩関節拘縮です。いずれも消炎鎮痛剤の内服、注射、リハビリなどにて治療を行います。
腱板断裂は、腕の骨と肩甲骨をつなぐ腱板といわれる板状の腱が切れたりして損傷される疾患です。原因として、転んだり、重い物を持ったりして損傷される場合と、使いすぎや加齢による腱板の老化により損傷される場合があります。治療として、まずは注射やリハビリによる保存療法が行われますが、断裂部が治癒することはありません。また、断裂部は経年的に大きくなるといわれており、断裂部が大きくなると手術で治すことが難しくなります。保存療法にて痛みが改善しない場合や、肩の挙上困難が続く場合は手術による治療が必要になります。
2023年10月号

私は子どもの頃に高熱でひきつけを起こしたそうですが、うちの子は大丈夫でしょうか?

両親や兄弟・姉妹が熱性けいれんを起こした子どもは、起こす確率が高いといわれています。ご両親の子どもの頃のエピソードを聞いておくことは参考になるので、不安なことがあれば、かかりつけの医療機関で相談をしてみてください。
小児科 糸山 綾
子どもの頃はよく高熱を出し、中にはひきつけ(けいれん)を起こす子どもたちがいます。乳幼児期(生後6か月から5歳)にみられる発熱に伴うけいれん発作のことを、熱性けいれんと呼び、髄膜炎や急性脳症、てんかんなどの病気とは区別されます。両親や兄弟・姉妹が熱性けいれんを起こした子どもは、起こす確率が高いといわれていますが、熱性けいれんの場合、多くは5分以内に自然に止まって、反応や受け答えができるようになり、熱が治る頃には普段通りの元気いっぱいの姿になります。
お子さんがけいれんする姿を想像することはとても怖く感じると思いますが、ご両親の子どもの頃のエピソードを聞いておくことは参考になるでしょう。不安なことがあれば、かかりつけの医療機関で相談をしてみてください。熱性けいれんの対応や注意点などについてお伝えします。
2023年9月号

健診の便潜血検査で陽性となりました。症状はありませんが精密検査を受けたほうが良いですか?

便潜血検査は、大腸癌の早期発見を目的として行われます。陽性であった場合でも必ずしも大腸癌が存在するわけではありませんが、大腸癌が早く見つかる機会だと考え、ぜひ精密検査を受けてください。
外科 柴 修吾
便潜血検査とは便の中の肉眼的にはわからないような微量の血液を検出する検査です。大腸癌の早期発見を目的として行われます。癌のほかポリープや、腸管の炎症、痔核などでも陽性となることがあり、便潜血検査が陽性であった場合でも必ずしも大腸癌が存在するわけではありません。
大腸癌は初期の段階ではほとんど症状がなく、進行するにつれ血便や腸閉塞(大腸が癌で閉塞すること)をきたします。大腸癌は早期のうちに治療を行うことにより治癒する可能性が高まります。
よく痔からのからの出血だろうと思って検査を受けない方もいますが、痔のほかに大腸癌やポリープが見つかる場合もあります。便潜血陽性となった場合大腸癌が早く見つける機会だと考えぜひ精密検査を受けてください。
2023年8月号

膝が変形していると言われ、もう何年も関節注射をしていますがよくなりません。他の治療法はないですか。

運動療法のほか、手術も選択肢の1つです。年齢、痛み具合、レントゲン所見などをふまえて、医師と相談してみてください。
整形外科 天野 滉大
60歳以上の人で疼痛を伴う変形性関節症の患者は、国内で6人に1人と知られています。はじめは関節内注射、鎮痛薬などで痛みを取りつつ運動療法を行うことが多く、それだけでよくなることが多いです。しかし、なかなか良くならない場合には手術も選択肢の1つとして挙がります。手術に関しては、膝関節鏡手術、骨切り手術、人工膝関節全置換術などが有名です。手術方法は、年齢、痛みの日常生活への影響具合、レントゲン所見などを中心に、患者さんご本人と相談し決定することになります。なかなか治らない痛みに困っていましたら、近医の整形外科の先生でも当院でもよいので、一度ご相談いただければと思います。
2023年7月号

経鼻内視鏡(鼻からの細い胃カメラ)と経口内視鏡(口からの普通の胃カメラ)どっちがいいのですか?

経鼻内視鏡は比較的楽に検査を受けることができますが、詳細な観察ができない可能性がある等のデメリットがあります。詳細な検査をご希望される方は経口内視鏡での検査を選択してください。
内科 辰巳 明久
経鼻内視鏡の最大のメリットは細くてのどの違和感が少なく、比較的楽に検査を受けることができることです。一方でデメリットは詳細な観察ができない可能性があることです。最新の経鼻内視鏡は技術の進歩により画質は経口内視鏡と遜色ないですが、細くコシがないことによる操作性の悪さや、送水機能が低いことで観察がしづらいことは避けならない問題です。
もし、詳細な検査をご希望される方は経口内視鏡での検査を選択してください。健診などで異常がない方の検査の場合は経鼻内視鏡でも十分観察可能であることが多いですが、メリットとデメリットを理解して選択してください。かかりつけ医がいる場合はよく相談して決めてくださると良いと思います。2023年6月号

関節が腫れて痛くなることが続きます。どのような病気が考えられますか?また、いい治療はありますか?

変形性関節症、関節リウマチ、痛風に伴うもの、皮膚や内科的疾患に伴って関節炎を引き起こすものなどが挙げられます。関節リウマチの治療では内服薬や注射薬、手術の方法があり、近年めざましく治療が進歩しています。
リウマチ科 小山 賢介
年齢的な要素やレントゲン所見によって、いろいろな病気が考えられます。変形性関節症、関節リウマチ、痛風に伴うもの、皮膚や内科的疾患に伴って関節炎を引き起こすものなどが挙げられます。レントゲンだけでなく血液検査、関節エコーなどを用いてようやく診断に至る場合もあります。
関節リウマチや乾癬性関節炎では近年めざましく治療が進歩しています。古くからある内服薬だけでなく、生物学的製剤という注射薬、注射薬と同等の効果を示すとされる内服薬も治療に使われています。一度変形を起こしてしまうといくら薬で治療しても変形が戻ることはありません。適切なタイミングに適切な治療を行うことが重要です。既に変形のある方、心配しないでください。手術の方法や使用する金属も日々進歩しています。リウマチ専門医にご相談ください。
2023年5月号

知り合いが腹痛で病院に行ったら虫垂炎と言われました。薬でよくなったようですが手術はしなくてもよいのですか?

昔と比べると、抗生剤で治癒する虫垂炎が増えたのは事実です。薬の治癒と手術それぞれ一長一短あるので、主治医とよく相談して治療方針を決定することが必要です。
外科 赤澤 祥弘
虫垂炎の治療には大きく分けて、抗生剤を使用して虫垂の中で増えたばい菌を退治する治療と、手術で虫垂を切除する方法があります。20年前や30年前に比べると抗生剤が進歩し、抗生剤で治癒する虫垂炎が増えたのは事実です。
ただ、どれぐらいの割合かははっきりしませんが、一度虫垂炎になった患者さんは再発してまた虫垂炎になる確率が高いともいわれています。抗生剤治療を選択してうまくいかなかった場合は虫垂に穴が開くこともあります。
2023年4月号

白内障手術をした友人に「早く手術したほうがいい」と勧められました。手術したほうがよいのでしょうか?

手術のタイミングは千差万別ですが、「生活に不便を感じている」「白内障が見えにくさの主因である」「手術の負担よりも手術による見え方の改善が大きい」の3つを満たした時は手術適応と考えられます。
眼科 葛西 友香
白内障とは眼の中の水晶体が白く濁り、視力低下、まぶしさ、光がだぶって見えるなどの症状をきたす病気です。原因の多くは加齢で、80歳を超えれば100%の方が白内障になります。最終的な解決策は手術ですが、白内障は程度に個人差が大きく、また生活や仕事、年齢、全身状態によっても必要としている見え方は人よって異なりますので手術のタイミングは千差万別です。
そのような中で眼科医が手術適応と考えるのは、「患者さんが生活に不便を感じている」「本当に白内障が見えにくさの主因である」「手術の負担よりも手術による見え方の改善が大きい」という3つの条件を満たした時と言えるでしょう。
2023年3月号

ハイハイをせずお座りのまま移動するのですが、大丈夫でしょうか。

ハイハイ以外の発達に気になる事がなければ、正常発達のバリエーションの一つの、座ったままお尻をいざらせて移動するシャフリングベビーかもしれません。
小児科 藤岡 かおる
ハイハイの時期の目安は生後8~10カ月頃ですが、個人差も大きいことが知られています。赤ちゃんは首がすわった後寝返りが可能になり、ハイハイ、つかまり立ち、独歩と段階を踏みながら発達していきますが、発達の過程もバリエーションがあります。
その一つが、ハイハイの代わりに座ったまま腰をゆすり移動するタイプで、シャフリングベビーと呼ばれます。その場合歩き始めが遅くなる傾向はありますが、その後ほとんどは正常に発達しますので大丈夫です。
ただ、中には神経の病気などが隠れていることもあるため、ハイハイ以外にも運動発達や手指の動きの発達が遅いなど気になる事がある場合は小児科に相談してみてください。
2023年2月号

70歳代女性。コロナ禍のため運動不足の状態で、半年前より両側の下腿がむくみ、最近では右下腿皮膚の一部が痒くただれてきています。

質問者の場合は、運動不足や肥満のため下肢から心臓へ還る血流が滞る慢性機能的静脈不全症が疑われます。下腿浮腫の病態は様々です。的確な病態の把握と治療が大切です。
外科 鈴木 修
下腿浮腫(むくみ)の原因として種々の疾患が挙げられ、片側例では ①深部静脈血栓症 ②炎症 ③膝関節等の術後 ④静脈瘤による血流障害 ⑤リンパ浮腫 ⑥脳梗塞後の片麻痺などが考えられます。両側例では全身的疾患が起因し ①心不全 ②腎不全 ③肝硬変、ネフローゼ、低栄養等の低蛋白血症 ④甲状腺機能低下 ⑤糖尿病 ⑥特発性などが考えられますが、複数の病態が合併することもあります。
質問者の場合は、運動不足や肥満のため下肢から心臓へ還る血流が滞る慢性機能的静脈不全症の病態が疑われ、静脈環流が増悪すると皮膚がただれ潰瘍化することもあります。下肢挙上、ストッキングによる圧迫、マッサージ、運動、減量、利尿剤などで治療を行います。
2023年1月号

糖尿病とスティグマ、アドボカシー活動について教えてください。

スティグマとは恥・不名誉な烙印を意味し、本人の意思と努力で克服できると思われがちな糖尿病はスティグマの対象となり得ます。世界的には、糖尿病患者さんの権利を守るアドボカシー(権利擁護)活動が注目されています。
内科 保阪 大也
世界的には糖尿病に関してのスティグマとアドボカシー活動が話題です。
スティグマとは:恥・不信用のしるし、不名誉な烙印、を意味します。ある特定の属性により、いわれのない差別や偏見の対象となることをいいます。病態で言えば、感染症、皮膚病など外見に特徴が出やすい疾患や、糖尿病、肥満など本人の意思と努力で克服できると思われがちな病気がスティグマの対象となり得ます。メディアの情報や友人、医療従事者からの助言、指導などがスティグマの発生源となります。助言するのにも否定的なニュアンスを含まないように配慮が必要とされます。
スティグマは自己肯定感の低下や社会的孤立、治療機会の損失につながるため、糖尿病患者さんの権利を守るアドボカシー(権利擁護)活動が注目されています。弱い立場の方を守るため、組織・社会・行政・立法に対して主張・代弁・提言を行うことを指します。学会の専門委員会の設立、患者会の活動と支援、米国ではインスリン薬価高騰に対する反対運動も行われています。
血糖が改善しないのを一番気にしているのは患者さん本人なので、ご家族、医療従事者はそんな意識を持ちながら協力、アドバイスをしていく心がけが必要です。
2022年12月号

虫のようなものが飛んで見えます。眼科を受診した方が良いですか?

それは飛蚊症と呼ばれるものです。加齢に伴うものであれば治療の必要はありませんが、原因によっては早期の治療が必要な場合もあり、早めの受診をお勧めします。
眼科 古畑 優貴子
白い壁や青空を見たときに、黒い点や透明な糸状のものが見える症状は飛蚊症と呼ばれるものです。多くの場合は加齢に伴うもので心配はありませんが、中には網膜剥離など放置すると失明に至る病気が原因となっていることもあります。
原因を調べるためには、検査用の目薬(散瞳薬)をつけて眼底検査をする必要がありますが、散瞳薬をつけると3~6時間程度、まぶしくてピントが合わない状態が続くため、その後にご自身で運転するのは危険を伴います。眼の状態によっては当日散瞳検査ができない場合もありますが、飛蚊症の精査を希望されるのであれば、どなたかに送迎を頼むか公共交通機関を利用して受診してください。加齢に伴う飛蚊症であれば治療の必要はありませんが、原因によっては早期の治療が必要な場合もあり、早めの受診をお勧めします。
2022年11月号

足の親指が外側に曲がり隣の指と重なり靴や靴下が履きづらいです。何かいい治療法はありませんか?

それは外反母趾という状態です。装具などで悪化を防ぐことはできますが、変形が進むと手術をしなければ治りません。
整形外科 小川 知周
それは外反母趾という状態です。原因としては遺伝的なものと、ハイヒールなどの生活習慣によるものがあります。軽い変形であれば装具などで悪化を防ぐことはできますが、趾(あしゆび)が重なるほど曲がってしまうと手術をしないと治りません。
外反母趾自体はそれほど強い痛みはでないことが多く放置している人も多いと思いますが、変形が進むと靴が履きづらくなったり、足底や趾にタコができそこが痛くなったりと日常生活に支障がでてきます。変形が高度になると2~5趾の変形も伴い、歩行にも支障が出てきます。日常生活に支障が出る前に整形外科の受診をお勧めします。
2022年10月号

鼠径ヘルニア(脱腸)とはどういう病気ですか?

足の付け根の「鼠径部」がふくらんでいる状態をいい、中高年の男性に多い病気です。放置をすると腸が壊死してしまうこともありますが、術後数日で退院が可能です。
外科 須貝 英光
足の付け根の「鼠径部」がおなかに力を入れるとふくらむ、常にふくらんでいる状態をいい、痛みを訴えて外来受診する方もいます。中高年で男性に多いです。嵌頓(かんとん)することがあり、緊急手術となることがあります。嵌頓とは腸がふくらむ部分にはまり込んでしまい、抜けなくなる状態です。腸閉塞症状(腹痛、嘔吐)がでて、放置すると腸に血流障害がおきて壊死してしまうことがあります。
治療としては下半身麻酔か全身麻酔下に鼠径部に5cm皮膚を切開し、ふくらんでいる部分をメッシュシートなどで補強します。メッシュシートなどの人工物を使用できない場合は、自分の筋膜で補強する場合もあります。腸が嵌頓していて腸を切除しなければならないときもあります。
全身麻酔下に数カ所穴をあけ、腹腔鏡下でおなかの中から内視鏡を使ってメッシュシートで補強する方法もあります。いずれも術後数日で退院が可能です。
2022年9月号

検診で脂肪肝ですが大したことないと言われたことがあります。放置してよいですか。

重い病態につながることがあり、放置は望ましくありません。
院長 井上 泰輔
脂肪肝は肝障害の原因として最も多く、近年では成人の健康診断受検者の約3割にみられます。原因の多くはアルコールと過栄養(食べ過ぎ、運動不足)です。アルコール性はもちろん、お酒を飲まない方にもみられる非アルコール性脂肪性肝炎(NASH ナッシュ)という病態では、肝硬変や肝がんといった重い病態につながることがあり、放置は望ましくありません。また糖尿病や高脂血症、高血圧、高尿酸血症などの生活習慣病も合併しやすいです。
節酒や減量を心掛けたうえでかかりつけの医療機関へ通院し、肝臓が固くなる兆候があれば肝臓専門医との連携が必要です。
2022年8月号

ロコモティブシンドロームという言葉を聞いたのですが、どんな病気ですか?

ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは病気ではなく、「運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態 」のことです。
整形外科 後藤 豪
ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは病気ではなく、「運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態 」のことです。
つまり、骨・関節・筋肉・神経などの運動のための身体の仕組みが障害され、立ったり歩いたりする能力が低下した状態がロコモなのです。ロコモが進行すると将来介護が必要になるリスクが高くなります。
自分がロコモか気になった方には、「ロコチェック」を調べましょう。
1.片脚立ちで靴下がはけない 2. 家の中でつまずいたりすべったりする
3.階段を上がるのに手すりが必要である 4.家のやや重い仕事が困難である
5. 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である
6.15分くらい続けて歩くことができない 7. 横断歩道を青信号で渡りきれない
一つでも当てはまった方はロコモの心配があります。片足立ちやスクワット等の習慣をつけ、元気な足腰を保ちましょう。
2022年7月号

保育園に通い始めてから毎月風邪をひきますが、免疫が弱いのでしょうか?

新しく入園する子にとっては、初めて多くの病原体にさらされることとなり、中には毎週のように風邪で熱を出すお子さんもいます。
小児科 大城 浩子
新しく入園する子にとっては、初めて多くの病原体にさらされることとなり、中には毎週のように風邪で熱を出し、入園しても殆ど通えないお子さんもいます。お子さんが本当に免疫が弱い場合は、ばい菌(細菌)による肺炎、重症な中耳炎、皮膚に膿(うみ)が溜まってしまうといった感染症を繰り返します。
また「風邪が1か月治りません」といって受診されるお子さんもいますが、1つの風邪を1か月も治せないということも殆どありません。風邪の治りかけの時期は、別の風邪ももらいやすい時期であり、連続で風邪にかかってしまうことが多く、咳や鼻水が長引いてみえるのです。
2022年6月号

膵臓癌が心配です・・。膵臓癌は早期発見できるのですか?

どういった人が膵臓癌を発症しやすいのかを知っておくことが重要です。
内科 髙橋 英
膵臓癌は特異的な症状に乏しく、残念なことに多くの方が進行癌として発見されます。2018年の癌死亡者数の全体4位と増加傾向にあり、5年生存率は8%と非常に低く、根治が難しい病気です。しかし腫瘍径が1cm 以下で見つかれば、80%以上の5年生存率が報告されており、早期発見により長期予後が期待できます。
膵臓癌を早期発見するためには、どういった人が膵臓癌を発症しやすいのかを知っておくことが重要となります。膵臓癌の危険因子として膵癌家族歴・喫煙歴・飲酒歴、合併症疾患として糖尿病・肥満・慢性膵炎・膵管内乳頭粘液産生腫瘍・膵のう胞などが挙げられています。上記危険因子が当てはまり、一度も膵臓の検査をしていない方は、一度、膵臓精密検査を受けることをお勧めします。
当院では専門医や検査機器も充実し、安心して診療を受けていただける体制が整っています。お気軽にご相談ください。
2022年5月号

お薬手帳をおもちですか?

お薬手帳を持参しましょう!処方の重複を防いだり、併用禁忌の薬を避けるためにもとても大切です。
内科 池田 フミ
新型コロナウイルス予防接種会場では、かかりつけ医ではない医師はお薬手帳を見て予防接種を受けても大丈夫かを判断します。血液サラサラの薬といっても抗凝固剤なのか抗血小剤なのかで対応は異なります。また高血圧や糖尿病、喘息といった慢性疾患の場合には内服、吸入薬の内容で患者さんの重症度やコントロールの状況がわかります。
かかりつけ医でない病院を受診する場合にもお薬手帳はとても大切です。お薬手帳をみれば薬の内容以外にも通院している医療機関、主治医の先生、かかりつけ薬局がわかります。内科、整形外科、耳鼻科などいくつかの医療機関に診てもらっている場合、同じようなお薬を重複して処方することや、併用禁忌の薬を処方することを避けることができます。お薬手帳を持参しましょう。
2022年4月号:お休み
2022年3月号

腸閉塞ってなんですか?

腸の流れが悪くなったり、ひどい場合は腸の血管が締め付けられて腸が腐ってしまったりする病気です。
外科 赤澤 祥弘
腸閉塞にもいろいろ種類があります。おなかの手術をするとその影響でおなかの中の臓器や脂肪が癒着をすることがあります。それが原因で腸自体がねじれてくっついたり、脂肪が絡まることにより腸が狭くなったりします。そのせいで腸の流れが悪くなったり、ひどい場合は腸の血管が締め付けられて腸が腐ってしまったりする病気です。
おなかの手術をしたことがない人でも、癌が原因になったり脱腸が原因でなったりすることがあるため、誰でもなりうる病気だと言っても過言ではありません。腹痛や嘔吐の症状があります。
また、排便や排ガスが止まりおなかが張ってきます。ただ、腸閉塞の程度によってはこのような症状がすべて出るとは限らないため、注意が必要です。
腸閉塞の診断となった場合は、どのような治療であってもまずおなかを休めることが必要なため入院が必要になります。
2022年2月号

健康診断にて視神経乳頭陥凹拡大と言われましたが何の病気ですか。

緑内障性の変化でみられる眼底所見ですが、生まれつき特殊な視神経乳頭の形状をしている場合もあり、その場合は病気ではありません。
眼科 重本 有実
視神経乳頭陥凹拡大は健康診断で指摘される眼科所見としては最も多い所見の一つです。視神経乳頭とは目の奥にある視神経の出口のことで、その凹みが大きいことを視神経乳頭陥凹拡大と言います。緑内障性の変化でみられる眼底所見となります。
ただし、生まれつき特殊な視神経乳頭の形状をしている場合もあり、その場合は病気ではありません。一度指摘された方は、眼科にて視野検査を受けて緑内障かどうか診断してもらう必要があります。
緑内障はかなり進行するまでほとんどの自覚症状がでません。また、一度視野障害がでてしまうと障害をうけた部分は治療で改善させることはできないため早期に発見し、悪化させないように治療をして定期通院を継続することが望ましいです。
2022年1月号

糖尿病の患者は認知症になりやすいのですか。

糖尿病患者さんの認知症発症率は、そうでない人と比べて2倍以上高いとされています。
内科 保阪 大也
日本のある疫学研究では、糖尿病患者さんの認知症発症率は、そうでない人と比べてアルツハイマー型も脳血管性のものも2倍以上高いとされています。インスリン作用不足で悪玉タンパク質が脳に溜まったり、動脈硬化で脳への血液供給が減ったりすることなどが原因です。
認知症は予防がとても大事です。いわゆる「頭の体操」も大事ですが、ハードウエアとしての脳機能を維持することも重要です。
日本人向けではないかもしれませんが、アルツハイマー協会の提唱する10の方法が参考になると思います。
1.健康的な食事:飽和脂肪酸や糖分、塩分を制限する、アルコール摂取を控えるなど
2.適度な運動習慣:ウォーキング週3回でも効果あり
3.高血圧や糖尿病を治療する:高血糖も低血糖も注意
4.禁煙する 5.良質な睡眠 6.精神的な健康の維持 7.社会的な交流の維持
8.知的な刺激を得る 9.学習する機会を得る
10.事故に注意:交通事故や転倒など、脳への直接的なダメージは深刻
結局基本的なことの継続が大事ということですね。
2021年12月号

薬により、1日2回、3回と服用回数が違いますが、守らないといけませんか?昼分の内服ができません。

1日の服用回数が違うのには、理由があります。内服が難しい時間がある場合は、ぜひ医師や薬剤師にご相談ください。
小児科 藤岡 かおる
1日の服用回数が違うのには、理由があります。薬によって効果の持続時間が違い、薬の効き目を維持するために1日3回の薬はおよそ8時間毎、1日2回の薬はおよそ12時間毎に服用するのが基本です。
特に抗生物質は1日3回の薬を2回で飲むと望んだ効果が得られなくなることがあります。内服時間の2-3時間のずれは問題がないので、昼の内服が難しい場合、起きたらすぐ1回目を内服し、15、16頃の夕方帰宅後すぐに2回目、寝る直前に3回目を内服するのでも構いません。生活スタイルなどによって、内服が難しい時間がある場合は、ぜひ医師や薬剤師にご相談ください。
9月16日付で着任しました小児科医の藤岡かおると申します。地域の皆さんのお役に立てるよう努力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
2021年11月号

検診の腹部エコー検査で胆嚢腺筋腫症と言われました。どんな病気でしょうか?

胆嚢の壁が厚くなる病気です。胆嚢腺筋腫症の約90%は胆石を合併すると言われています。
外科 平井 優
胆嚢腺筋腫症は、専門的に説明するとロキタンスキー・アショフ洞の増生により胆嚢の壁が厚くなる病気です。胆嚢の内圧上昇や、胆嚢収縮機能異常により反応性に胆嚢の壁の筋肉が肥厚し粘膜上皮の過形成を招きます。エコー検査や、CT、MRIの画像診断で発見され、分節型・限局型・びまん型に分類されます。
胆嚢腺筋腫症の約90%は胆石を合併すると言われています。胆嚢腺筋腫症は悪性疾患ではないので、確実に胆嚢腺筋腫症の診断がつけば経過観察のみで良いです。しかし、癌などの胆嚢の壁肥厚を伴うような悪性疾患との鑑別が困難な場合や、腹痛や発熱などの症状を起こす胆石を合併する場合は胆嚢の摘出術をお勧めすることもありますので、担当医と相談してみてください。
2021年10月号

60歳代男性。検診のエコーで胆嚢の腺筋症を指摘されましたが、どのような病気でしょうか?

胆嚢の壁が小嚢胞(水の袋)や石灰化を伴い部分的または全体に厚くなる病態です。
外科 鈴木 修
胆嚢の壁が小嚢胞(水の袋)や石灰化を伴い部分的または全体に厚くなる病態で、粘膜が隆起するポリープとともに、癌との鑑別を必要とする疾患です。
発生原因として慢性炎症等が挙げられますが詳細は不明で、健常者の2~5%程に認められると考えられています。限局型・分節型(胆嚢中央部付近に発生)・全般型の3つに分類され、多くは無症状で検診のエコー検査で指摘されることがほとんどですが、胆石にて胆嚢炎を発症し腹痛を自覚することもあります。胆嚢癌との関連性は不明ですが、分節型にやや多いと報告されています。
【治療】
腹痛などの症状、胆嚢癌との鑑別困難、分節型で胆石合併、結石充満などの人では腹腔鏡下胆嚢摘出を考慮します。それ以外の人は6~12か月毎にエコーなどで経過を観察することが推奨されています。
2021年9月号

新型コロナワクチンを2回接種すればマスクや手の消毒等の感染対策は不要ですか?

会話の際や室内においてはマスクの着用が必要です。手洗いや消毒も引き続き行う必要があります。
院長 東田 耕輔
会話の際や室内においてはマスクの着用が必要です。手洗いや消毒も引き続き行う必要があります。
ワクチン接種により、接種後感染しても、重症化や周囲への感染も抑えることが出来ます。米国のワクチン接種責任者は、新型コロナで死亡された方の99%はワクチンを打っていなかったと言っています。効果は明らかです。
変異株にはワクチン効果が減弱してきていますが、マスクと手指衛生、充分な換気を併せれば、少人数での会食や家庭内での感染リスクもさらに下げることが可能です。
我々の目標は、クラスターを防止し、新型コロナに打ち勝ち、以前の生活を取り戻すことです。
このウイルスの特徴は、感染しても無症状の人が多いことです。市民の皆さんには、室内や会話時のマスク着用は習慣としていただきたいと思います。生活自体を新型コロナ仕様に変えることが必要です。
2021年8月号

検診で膵のう胞と言われました。どのような病気が考えられますか。

内科 早川 宏
のう胞は液体のたまった袋のことです。検診でいろいろな臓器ののう胞を指摘されることはあると思います。肝臓や腎臓ののう胞の多くは腫瘍と関係しないものであり、問題ないことが多いです。
しかし膵臓ののう胞は多くが「腫瘍性」であり、精密検査や経過観察が必要です。多くが良性であるため過剰な心配は不要ですが、まれに悪性化することもあります。
膵臓の病気は治療が難しいと言われますが、早く見つけることで良い結果に結びつけることができます。
当院では専門医や検査機器も充実し、安心して診療を受けていただける体制が整っています。
お気軽にご相談下さい。
2021年7月号

白内障と診断されたら手術を受けなくてはならないのですか?

デメリットや感染のリスクなどもあるため、主治医と相談のうえ、患者さんご自身で決めていただくこととなります。
眼科 古畑 優貴子
白内障の原因として糖尿病はアトピーなどが影響することもありますが、一般的に50歳以上の人にみられる白内障の多くは、白髪や肌のしわと同じ加齢現象で、程度には個人差があります。
白内障による視力低下で生活に不便を感じるようであれば手術という選択肢が出てきます。
白内障以外の眼の病気がすでにある、これから発症しそう、というような状態のときに、患者さん自身が見え方に困っていなくても眼科医が白内障手術を勧めることもありますが、
白内障だけであれば手術はご本人の希望次第です。
術後はピント調節ができなくなるといったデメリットや感染のリスクなどもあるため、手術を受けるかどうかは主治医と相談のうえ、患者さんご自身で決めていただくこととなります。
2021年5月号

長く立っていたり、歩いたりするとお尻から太ももにかけて痛くなります。何か病気でしょうか?

いくつか原因が考えられます。お近くの整形外科を受診するようにしてください。
整形外科 小川 知周
いくつか原因が考えられます。一番多いものは腰の骨の所で神経が圧迫されてお尻や足の方に痛みが走る神経痛です。
若い人では腰椎椎間板ヘルニアなどが原因になります。もう少し年齢が上の方は腰部脊柱管狭窄症などの骨の変形により神経痛が出現します。
腰の骨以外の原因としては股関節の変形による痛みの場合もあります。
あとは稀ですがお尻の筋肉により神経が圧迫される梨状筋症候群という病態もあります。
いずれにしても腰や股関節などの検査をしないとわかりません。
放置していてもなかなかよくならないと思いますので、お近くの整形外科を受診するようにしてください。
2021年3月号

感染対策でマスクをするようになってから、あご周辺の肌荒れに悩んでいます。どのように対策したら良いでしょうか?

バリア機能を保つためには、スキンケアでの保湿が大切です。
小児科 斎藤 衣子
長時間マスクをしていることで、マスク内が蒸れて温度、湿度が上昇します。すると皮脂が増えて毛穴に詰まり、雑菌が繁殖してニキビができやすくなります。
一方でマスクを外す時に内部の湿気が急激に蒸散し、肌内部の水分が奪われると、肌の乾燥が進みます。
またマスクの着脱を繰り返したり、マスクをずらしたりすることでマスクと肌の間に摩擦が生じ、肌のバリア機能が低下します。このようにムレ・乾燥・摩擦を繰り返すことで肌はデリケートな状態になっています。バリア機能を保つためには、スキンケアでの保湿が大切です。
夜には、低刺激の化粧水や乳液で保湿をしましょう。また、摩擦が気になるあご、耳の後ろなどはワセリンをあらかじめ塗っておくのも良いでしょう。
不織布マスクが合わない方はガーゼなどの柔らかい素材を挟むと肌への刺激を和らげます。
2021年2月号

五十肩は放っておけば治るのですか?

全ての人が治るわけではなく、時に後遺症を残すこともあります。
整形外科 神平 雅司
全ての人が治るわけではなく、時に後遺症を残すこともあります。
40歳以上になると、明らかな原因がなく肩の痛みが出現することがあります。
四十肩、五十肩と自己判断し、放っておけば治るものと考える方が多いと思います。
確かに1〜2年のうちに症状が改善するものもあります。
しかし発症後数ヶ月すると肩関節の動きが悪化して衣服の着脱が困難になり、夜間の痛みのために不眠になることがあります。
五十肩になると関節を動かした方がよいといいますが、下手に動かすとかえって悪化します。
さらに五十肩だと思っていたら肩の腱が切れていたということもあります。
五十肩かなと思ったら早めに整形外科を受診して、五十肩かどうかを診断し、適切な治療を受けることが少しでも早く治るために重要です。
2021年1月号

糖尿病があると新型コロナが重症化しやすいと聞きます。実際どうなのでしょうか。

確かに、糖尿病患者さんは感染症にかかりやすく、重症化しやすいことが知られています。
内科 保阪 大也
確かに、糖尿病患者さんは感染症にかかりやすく、重症化しやすいことが知られています。血糖が高いことで白血球や免疫細胞などの運動能力や殺菌力が落ちてしまったり、血流障害で薬や栄養が行き渡らない、炎症の治りが遅いなどが原因です。新型コロナに限らず、他の呼吸器感染や、尿路、胆道、皮膚の感染、そして歯周病や思わぬケガ、傷も問題となります。
普段の血糖管理をしっかり行うこと、体調管理(熱や傷の有無、お通じや尿の様子の観察など)に気を配ること、手洗いや歯磨きの励行、体の清潔維持、予防接種などが対策として挙げられるでしょう。
体には厳しい季節なので体調が悪いときは主治医によく相談して乗り切りましょう。
2020年12月号

コロナ禍で3密を避けた方がよいのだとは思われますが病院への受診は大丈夫なのでしょうか?

当院では発熱者外来を設けることによってほかの患者様と区別したり、待合室が密にならないように席を空けて座っていただいたりしています。
外科 赤澤 祥弘
当院では発熱者外来を設けることによってほかの患者様と区別したり、待合室が密にならないように席を空けて座っていただいたりしています。
また、患者様皆さんの協力のもと入り口での問診や検温も実施させていただいています。症状があるのに受診を先送りにしたりすることで命を脅かす病気の診断が遅れることもありますので「コロナが落ち着いてからにしよう」という考えは持たずに、受診することにしましょう。
新型コロナウィルス感染症は恐ろしい病気ではありますが2,3か月受診が遅れることによって手遅れになる病気もたくさんあります。当院では、例年に比べて癌の手術件数が少ない傾向にあるようです。あくまでも個人の見解ですが、新型コロナウィルスによる「受診控え」や「健康診断敬遠」が少なからず影響しているものではないかと考えます。
2020年11月号

昨夜から38度の発熱があります。新型コロナ肺炎も心配です。
病院へすぐに受診した方が良いでしょうか。

新型コロナウイルス感染症患者には発熱や味覚障害などの軽症者から肺炎重症者までいます。また、発熱する病気は新型コロナウイルス感染症だけではありません。まずはかかりつけの先生にご相談しましょう。
内科 池田 フミ
新型コロナウイルス感染症患者には発熱や味覚障害などの軽症者から肺炎重症者までいます。診断のためにウイルスのPCR検査や抗原検査が必要となりますが、ウイルス検査はいつでもどこでもできるわけではありません。発熱患者さんに対応できるように医療機関は新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者さんとその他の患者さんが一緒にならないように感染対策をして診療を行っています。あらかじめ連絡をしてから受診することをお勧めします。医療機関を受診することで新型コロナウイルスに感染することを懸念して、かかりつけ医への受診を控える患者さんも多く見受けられます。高血圧や糖尿病のコントロールが悪くなり、持病が悪化することもあります。
また、発熱する病気は新型コロナウイルス感染症だけではありません。インフルエンザや細菌性肺炎、尿路感染、消化器系の病気での発熱など、診察して鑑別しなくてはならない病気はたくさんあります。受診を控えることで重症化して治療が遅れてしまうことが心配です。まずはかかりつけの先生にご相談しましょう。
2020年10月号

手指がしびれる手根管症候群とはどのような疾患ですか?

主に母指、示指、中指を中心にしびれ、痛みが出現する疾患です。40~60代にかけての発症が多く、女性の頻度が高いとされています。
整形外科 松木 寛之
主に母指、示指、中指を中心にしびれ、痛みが出現する疾患です。40~60代にかけての発症が多く、女性の頻度が高いとされています。多くは原因不明ですが、閉経、妊娠、骨折、手の使い過ぎなどが誘因となることがあります。就寝中や明け方に症状が強くなることが多く、薬指では中指側のみにしびれや感覚異常を認めるのが特徴です。
身体所見やMRI、電気生理学的検査等にて診断を行います。治療としては、手をよく使う作業を控えて安静を保つ、内服薬の服用、手根管部への注射などがあります。症状の程度にもよりますが、それらの治療にて5~6割の方に症状の改善が認められます。症状の改善が認められない場合や、手のひらの母指のつけ根がやせてきて小さい物がつまみづらくなったり、細かい作業が困難となった場合は手術が必要になります。
手術は、1.5~2cmの切開にて、時間は10分程度で、日帰り手術にて行えます。手根管症候群が疑われるようでしたら、当院にご相談ください。
2020年9月号

コロナが心配で、小さいこどもを医療機関に連れて行きたくないのですが、予防接種はしないとだめですか?

予防接種はぜひ、受けていただきたいです。現在、医療機関では感染症の方とそうでない方を、時間や場所を分けて診察する工夫をしています。
小児科 溝呂木 園子
予防接種はぜひ、受けていただきたいです。私たちは、細菌やウイルスによる様々な感染症にかかります。これらを予防するために最も有効な手段がワクチンで、細菌やウイルスを精製・加工して、体にとって安全な状態にしたものです。本当にかかる前に、ワクチンを接種すること(予防接種)で、その感染症に対する免疫を作っておくことができます。その免疫によって、体が守られ、発症や重症化が避けられます。予防接種をすると、周囲の人への感染のリスクを減らすこともできます。有効な予防法がない感染症も多い中で、ワクチンで予防できる病気は予防接種をすることが最善の方法と考えられます。現在、医療機関では感染症の方とそうでない方を、時間や場所を分けて診察する工夫をしています。ぜひ、かかりつけの医療機関に相談してください。
2020年8月号

検診のエコーで「胆石がある」と言われました。どうしたらいいでしょうか?

症状のない胆石は特に治療の必要はありませんが、一度でも症状のある患者さんは病院で検査・治療を受けることをお勧めします。
外科 平井 優
胆のうは肝臓で作られる1日500~1000mlの胆汁を一時的に貯蔵する貯蔵庫として働いています。
胆汁には胆汁酸、胆汁色素(ビリルビン)、コレステロール、レシチンなどの成分と多量の水分が含まれています。胆のうはこの水分を吸収して、濃厚な胆汁へと変えますが、同時に粘液を分泌して濃縮胆汁成分による自らの損傷を防いでいます。
胆汁中のコレステロール過飽和、胆のう収縮機能低下、胆のうの変形などによる胆汁うっ滞、溶血性疾患等が原因で胆石が出来ると言われています。胆石がある人の90%以上の人は無症状です。ただし、一度症状のあった胆石患者さんは症状再発の可能性が高く、上腹部痛、背部痛、吐き気、発熱と強い右季肋部痛、黄疸、肝機能障害、膵炎等を起こします。
症状のない胆石は特に治療の必要はありませんが、一度でも症状のある胆石患者さんは病院で検査・治療を受けることをお勧めします。
2020年7月号

健診の腹部エコーで胆管拡張、膵管拡張を指摘されました。どういうことでしょうか?

胆管拡張、膵管拡張の原因は、胆管癌や膵臓癌などの悪性腫瘍、結石(胆石、膵石、胆管結石)、先天性、加齢性など様々な疾患があります。
内科 深澤 佳満
胆管は肝臓で作られる胆汁を流す管のことで、肝臓から十二指腸まで繋がっています。
また膵管は膵臓で作られる膵液が流れる菅のことです。胆管、膵管は最終的に1本の管(共通管)となり、十二指腸の乳頭部という部分へ閉口しているといった仕組みになっております。胆管の太さは7mm以下(胆嚢を摘出されている方は11mm以下)、膵管の太さは3mm以下が正常とされており、胆管の太さが7mmを超えると胆管拡張、膵管の太さが3mmを超えると膵管拡張となります。胆管拡張、膵管拡張の原因は、胆管癌や膵臓癌などの悪性腫瘍、結石(胆石、膵石、胆管結石)、先天性、加齢性など様々な疾患があり、外科手術や内視鏡治療などの処置が必要な疾患もあれば、経過観察でよい疾患もあります。御心配な方は一度検査を受けることをお勧めします。
2020年6月号

新型コロナウイルス感染が重大な問題になっています。手指衛生について教えてください。

手指衛生で重要視すべきは、①タイミングと②手指衛生の質です。繰り返し手指衛生を行うことで感染を防ぐことが可能です。
院長 東田 耕輔
新型コロナウイルスは、環境生存性が高く、様々な場所で数日以上生存可能です。手指衛生(アルコール消毒や石鹸での手洗い)で重要視すべきは、①タイミングと②手指衛生の質です。外出すると色々な場所を触ります。このウイルスが付着した手で、鼻・口・眼を擦ると、粘膜から感染する危険性があります。繰り返し手指衛生を行うことで感染を防ぐことが可能です。
エレベーターのボタン、室内の手すり、スイッチ類、ドアノブ、つり輪等多くの人が触る場所への接触後、帰宅時、食前、トイレの前後、店舗等への入出時などで手指衛生が必要です。手指衛生の質とは、手の洗い方や消毒の手順です。手・手首までの全ての部位の手指衛生を行う意識が重要です。全てを洗う方法を身につけてください。
充分な感染対策を計り、この危機を一緒に乗り越えましょう。
2020年5月号

健診にてLDLコレステロール(-C)が158mg/dlと異常を指摘されました。現在無症状ですがどのような注意が必要でしょうか?

長期間放置すると無症状のうちに動脈硬化が進行し、脳梗塞・心筋梗塞・足壊疽の原因になります。
外科 鈴木 修
LDL-C(悪玉) 140以上、HDL-C(善玉)40未満、TG(中性脂肪)150以上が脂質異常症の基準とされ、長期間放置すると無症状のうちに動脈硬化が進行し、脳梗塞・心筋梗塞・足壊疽の原因になります。とくにLDL-Cのコントロールが大切で、年齢(男性45歳以上、女性55歳以上)・高血圧・糖尿病・喫煙・家族歴・低HDL-C等の危険因子がない人では160未満ですが、危険因子を認める人はその程度に準じ120~140未満、心筋梗塞等を患ったことが有る人は100未満にすることが目標となります。脂質異常症を改善するためには、摂取カロリーを制限し動物性脂質を控えたバランスよい食事習慣、ウォーキング等の有酸素運動を1日30分以上、禁煙などの生活習慣が大切であります。
遺伝性や甲状腺機能低下症が原因のこともあり、また‘動脈の硬さ’を測定することで動脈硬化の状態を推測することも可能なため、医療機関にて相談して下さい。
2020年4月号

AI(人工知能)は昨今話題になってきており、日常生活の中にもいろいろと役立てられてきていますが、医療の分野ではどうですか?

医療の分野でも病気の診断などにAIを活用する研究が進められており、一部では既に実用化されているものもあります。
内科 三澤 明彦
AI(人工知能)はさまざまな分野で活用が進んでおり、医療の分野でも病気の診断などにAIを活用する研究が進められており、一部では既に実用化されているものもあります。
例えば、レントゲンやCT、MRIなどの画像診断や内視鏡の画像診断に関して、その膨大な画像(何万もしくは何十万もの画像)をディープラーニング(深層学習)させる事によって、熟練した専門医とほぼ同等(あるいはそれ以上)の診断が可能となってきました。消化器内視鏡の分野では、大腸内視鏡の超拡大観察に対して、病変部が腫瘍(癌)であるのか、非腫瘍(良性)であるのかを、AIで診断する内視鏡画像診断支援ソフトが内視鏡大手のO社により2019年春に発売され、実用化されました。(EndoBRAIN)
AIソフトのメリットは、初心者や非熟練者による病変の見落としを防げる、熟練者でも疲労や体調や忙しくて集中力が低下する等による見落としの可能性がなくなり、人間によるバラツキがなくなり、高い診断能が保てる、また人間では診断するのにある程度時間を要し、処理出来る数も限度があるが、AIでは短時間(瞬時と言ってもいい程)で診断可能で、人間のように疲れることなく、休みなく診断が可能であることなどです。
近い将来、ウェラブルセンサー(例えばAIウォッチの様な時計型や超薄型の絆創膏型など)を身に着ける事によって、今の自分の健康状態を病院に行かなくてもかなり詳しく分かる様になるかもしれません。
2020年3月号

「膝の水を抜くと癖になる」って本当ですか?膝に注射した日に入浴はしないほうがいいですか?

注射自体により感染を起こすことはあっても、入浴により感染を引き起こすことはありません。
整形外科 小川 知周
膝の水は、痛風やリウマチなど関節の病気、半月板や軟骨の損傷、使いすぎによる炎症など様々な原因で溜まります。水を抜くから貯まるのではなく、その原因をはっきりさせ治療しないと溜まり続けます。膝に水が溜まり屈伸しづらい、歩きづらいなどの症状がある場合は水を抜くことをお勧めします。
また注射した後、針を刺した穴はすぐ塞がるので、入浴しても水や菌が入ることはありません。注射自体により感染を起こすことはあっても、入浴により感染を引き起こすことはありません。論文も数多く発表されています。注射した日でも安心して入浴してください。
2020年2月号

子どもがノロウイルスの胃腸炎と診断されました。家族にうつらないようにするにはどうすれば良いでしょうか?

ノロウイルスは乳幼児から高齢者まで幅広い年齢の方に胃腸炎を引き起こすウイルスで、主に冬に流行します。
小児科 斎藤 衣子
ノロウイルスは乳幼児から高齢者まで幅広い年齢の方に胃腸炎を引き起こすウイルスで、主に冬に流行します。腹痛、下痢、嘔吐の症状が主で潜伏期間は24−48時間です。
有効な抗ウイルス剤はなく、脱水に対して経口補水液を利用するなどの対症療法が主です。
ノロウイルスはほとんどが経口感染で、カキなどの二枚貝を摂取することで感染しますが、感染者の便や吐物に触れた手を介しても感染します。手洗いが最も有効な予防法です。オムツや吐物の拭き取りに使用したペーパータオルはビニール袋に密閉して捨て、ふき取った後の床は次亜塩素酸で消毒しましょう。
家庭用の塩素系漂白剤でも代用できます。トイレの便座の消毒にも次亜塩素酸は有効です。
また、ウイルスが飛び散らないようにフタをしてから流すことも忘れずに行いましょう。
2020年1月号

手は上まで挙がるのですが、後ろにやると肩が痛く、夜間もとても痛みます。放っておいてよいでしょうか。

肩の前の方に、上腕二頭筋長頭腱(じょうわんにとうきんちょうとうけん)という力こぶの筋肉からつながる腱があり、これが炎症を 起こし、切れかかっているのです。
整形外科 神平 雅司
肩の前の方に、上腕二頭筋長頭腱(じょうわんにとうきんちょうとうけん)という力こぶの筋肉からつながる腱があり、これが炎症を起こし、切れかかっているのです。
草取りや雪かきをした後などに痛みが強くなります。肩の骨の前の方の尖ったところを押すと痛く、手を後ろに回すと痛いのが特徴です。この腱は自然に切れる人もあります。切れると腕の力こぶがアニメのポパイのようにだんご状にふくらみますが、痛みは軽くなり、放置してもさほど困ることはありません。しかし、なかなか切れずに強い痛みが続くことがほとんどです。
原因は、この腱の使い過ぎで腱が劣化しているのです。治療は、湿布や注射で痛みを軽くするようにしますが、痛みを繰り返すことがほとんどです。このような方は、肩のほかの大事な腱が切れて手術が必要になることがあります。
2019年12月号

高齢の親戚が何人か心不全で入院しました。患者が増えていると聞いていますがどんな病気でしょうか。

心不全とは、心臓の働きが悪くなることで、むくみや呼吸苦が起き、徐々に悪化して寿命を縮める病気です。
内科 保阪 大也
心不全とは、心臓の働きが悪くなることで、むくみや呼吸苦が起き、徐々に悪化して寿命を縮める病気です。超高齢化社会となり、年々増加しています。初期は自覚症状が少ないですが、入院するくらいになると、再発をしやすくなり、生命に関わってきます。
原因としては、1.高血圧症、2.心筋症(心臓の筋肉の病気)、3.狭心症・心筋梗塞(心臓に栄養を送る血管の病気)、4.心臓弁膜症、5.不整脈、6.先天性の心疾患等があります。
予防が困難な病態もありますが、喫煙や飲酒、食事、塩分摂取、運動習慣の是正で防げたり、進行を遅らせることもできます。現在高血圧、高脂血症、糖尿病他、上記の治療を受けている方は、その管理も重要です。
日常生活の改善や、自覚症状の変化に注意して、健康の維持に努めましょう。
2019年11月号

マムシに咬まれたときはどうすればよいですか?

咬まれた位置をまず心臓より低いところに保ち、咬まれた位置より心臓に近い部分をゴムなどで適度に縛り、できるだけ早く受診し てください。
外科 赤澤祥弘
マムシは4月~10月の温かい時期に活動が上がる生き物です。草むらやわらの中に手を入れたら激痛が走ったといい来院されます。咬まれた位置をまず心臓より低いところに保ちます。咬まれた位置より心臓に近い部分をゴムなどで適度に縛ります。できるだけ早い受診もしくは医療機関への連絡を心がけてください。ただ、アナフィラキシーショックが起こらなければ咬まれてすぐに死に至るような毒ではないので落ち着いて行動するようにしましょう。来院後は原則入院が必要になります。マムシの毒は出血毒と言って、皮膚の下や筋肉の間で出血し、咬まれた位置から徐々に腫れてきますが、2~3日でピークに達し約2週間で腫れは落ち着いていきます。毒の影響で腎臓の機能が悪くならなければマムシの毒で命を落とす可能性は低いと言われています。
2019年10月号

RSウイルスが流行していると聞きました。どんなウイルスですか?

秋から冬に流行し、主に乳幼児が感染し、時には呼吸困難に陥ることもある呼吸器感染症です。
小児科 溝呂木園子
秋から冬に流行し、主に乳幼児が感染し、時には呼吸困難に陥ることもある呼吸器感染症です。近年は流行期が早まり、夏から流行することも多くなっています。潜伏期間は5日前後で、接触や飛沫(咳やくしゃみ)で感染します。症状は発熱、鼻汁、咳、喘鳴(ぜいぜいする呼吸)です。大きいお子さんや成人では軽いかぜ症状程度ですむことが多いのですが、乳幼児(特に1歳未満の乳児)では、急性細気管支炎や肺炎などで呼吸困難をきたすこともあります。症状は1週間程度続きますが、乳幼児では1か月近く持続することもあります。抗原の迅速検査で診断することができますが、対象は1歳未満と入院児です。有効な治療法はないため、症状に応じた治療を行います。流行期には、乳児の重症化に注意が必要です。
2019年9月号

テニス肘とはどのような疾患ですか?

物をつかんで持ち上げる動作やタオルをしぼる動作などをした際に、肘の外側から前腕にかけて痛みが出現する疾患です。
整形外科 松木寛之
上腕骨外側上顆炎ともいわれ、物をつかんで持ち上げる動作やタオルをしぼる動作などをした際に、肘の外側から前腕にかけて痛みが出現する疾患です。30~50代にかけての発症が多く、女性に多い傾向があるといわれています。手首を伸ばす働きをする筋の起始部が肘外側部で障害されることが原因と考えられています。テニスプレーヤーに生じることが比較的多いのでテニス肘と呼ばれています。治療としては、手をよく使う作業やスポーツを控えて安静を保つ、テニス肘用のバンドの装着、手首や指のストレッチ、湿布や内服薬の使用、肘外側部への注射などがあります。半年から1年以上強い症状が持続し、慢性化している場合では、手術が必要になる場合もあります。手術療法には、病巣部切除術、肘関節鏡視下手術などがあります。肘の痛みで困っているようでしたら、当院を受診してください。
2019年8月号

胸部CT検診で精密検査を受けたところ「非結核性抗酸菌症」といわれました。どのような病気なのでしょうか。

「非結核性抗酸菌症」は最近増えている病気で、土や水、ほこり等の生活環境の中に存在する菌でおこる病気です。
内科 池田フミ
「非結核性抗酸菌症」は最近増えている病気です。土や水、ほこり等の生活環境の中に存在する菌でおこる病気です。結核菌との違いは人から人へ感染することがないことです。感染しにくい菌ですが、どうして発病するのかまだはっきりわかりません。女性にやや多く、年間約8000人が発症します。肺結核は年々減少していますが、近年増加傾向です。進行も5から10年と遅く感染の初期には自覚症状もないことがほとんどです。胸部CT検診の導入により発見されることも増えています。進行すると微熱、咳、痰、血痰などの症状が続きます。治療は症状や年齢を考慮して薬物療法が主体となります。若年者では手術をすることもあります。薬物療法はクラリスロマイシン、リファンピシン、エサンブトールの3種類の薬を1年から数年間内服します。呼吸器内科専門医への受診をおすすめします。
2019年7月号

近所のクリニックを受診して癌と診断されました。びっくりして不安でどうしたらいいのか分かりません。

癌(特に消化器癌)でお困りの方はまず当院外科の受診をご検討下さい。
外科 平井優
当院外科では、私を含め大学病院などで修練を積んだ外科医3名が勤務しています。
食道癌、胃癌、大腸癌、肝臓癌、胆道癌、膵臓癌、乳癌等の癌に対して手術療法を中心に抗癌剤治療を行ったり、不幸にも癌が再発してしまった場合の緩和医療を行ったり幅広い治療を行っています。
手術に関しては、患者さんの負担を軽くするような腹腔鏡下手術などの最新の術式を導入することはもちろん、手術日程に関しても極力患者さんの都合を最優先して決めるようにして、患者さんの利益の尊重に努力しています。
また癌治療では、手術は治療のスタートです。術後の再発予防の抗癌剤治療や、術後の体調不良等に対応するため、当院外科では手術・退院後も曜日や時間に関わらずきめ細やかな診療を心掛けています。地域の患者さんが、ご自宅近くの病院で癌の治療が完結できるようにお手伝いしますので、癌(特に消化器癌)でお困りの方はまず当院外科の受診をご検討下さい。
2019年6月号

検診で膵嚢胞を指摘されました。どのようなものなのでしょうか?

膵臓の内部や周囲にできる液体の貯まった袋のようなもののことであり、
病名を表すものではありません。
内科 深澤佳満
今年度から韮崎市立病院に赴任することになりました消化器内科の深澤佳満です。消化器の中の特に胆膵領域を専門にしておりました。よろしくお願いします。
膵嚢胞とは膵臓の内部や周囲にできる液体の貯まった袋のようなもののことであり、病名を表すものではありません。膵嚢胞にはさまざまな疾患が含まれており、疾患ごとに対応が異なります。膵嚢胞の大部分は膵管の中に粘液が貯留している膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)というものです。IPMNの中でも、経過観察でよいもの、内視鏡を用いた精密検査が必要になるもの、手術が必要となるものもあります。またIPMNのある場所とは別の場所に膵癌が出現してくる可能性があると言われており注意が必要です。御心配な方は一度検査を受けることをお勧めします。
2019年5月号

「人生会議(ACP)」とはどんな会議ですか?

「人生の終末期をどう過ごすか?」という話し合いです。
院長 東田耕輔
最近、終活としてご家族で人生の最後のステージについて話し合い、「終活ノート」として残す方が多くなりました。高齢になると急に病気を発症したり、悪化し、意識をなくしたり、同時に重大な合併症を患うことも増えます。意思表示のないまま、急変し救急車等で病院に運ばれると、多くの医師は気管内挿管等の集中的な救命治療を優先するよう教育を受けています。
治療を開始する前にご家族に伺っても、話し合いわれていないためどうするか判断できないことが多々あります。終活の延長として、”いざ”となる目にご家族等と人生会議を開いて、自分にとっての幸福な人生の最終章について話し合っていただきたいと思います。ご家族がいらっしゃらない場合は、介護担当者やかかりつけ医師、看護師等にご相談ください。
ぜひ、いろいろな希望すること、希望しないことを終活ノートに残してください。希望が変われば、書き換えることに何ら問題はありません。“縁起でもない”は忘れ去りましょう!
2019年4月号

肩甲骨を動かすことが、肩こりや肩の痛みに、そして精神的にもよいと聞きましたがほんとうですか?

ほんとうです。
整形外科 科部長 神平雅司
人は、加齢、運動不足、肥満などで猫背になります。
猫背になると肩甲骨は、お辞儀するように前に傾き、これに加えて背中の中心から外側に位置するようになります。 そうなると首や背中と肩甲骨をつなぐ筋肉が常に引っ張られます。また猫背の人が、顔を前に向けるには、首をそることが必要となるので首の筋肉にも負担がかかり、肩こり、頭痛を生じます。さらに肩甲骨の位置が外側になると、腕をあげにくくなるので肩関節にも負担がかかり痛みを生じます。
思いきり胸を張って両方の肩甲骨の内側がくっつくようにしながら肩甲骨をゆっくりと上下させます。痛みを感じてもゆっくりと大きく動かしてください。
この運動を1日に何度も行うことを習慣にしてください。背筋が伸びて視線が前を向くようになり、気持ちも前向きになるでしょう。肩甲骨ヨガが心身によいというのも、このためです。
2019年3月号

腸内細菌が色々な病気に関連があると聞きましたが、どんな病気と関連があるのか教えて下さい。

腸内細菌は下痢や便秘といった便通に関わっているだけでなく、色々な難治性の疾患の発症に関係していることが、近年の研究で 段々と分かってきました。
内科 副院長 三澤 明彦
例えば、関節リウマチの患者にみられるリウマトイド因子の標的は従来不明とされてきましたが、腸内細菌由来の抗体が高率に認められ、それが関節リウマチの発症に関わっていると考えられてきているようです。
また、慢性腎臓病(CKD)は便秘を伴うことが多く、腸内細菌が乱れており、新しい便秘薬(ルビプロストン)によって腎機能低下の改善がみられた報告もあります。
また、非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDS)による小腸潰瘍の発症にはグラム陰性菌が関与していることが報告されています。
また、細菌由来のエンドトキシン(細菌内毒素)は強力な肝障害の因子ですが、近年腸管の物質透過性が障害されることで、血中のエンドトキシン量が上昇し、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)の発症に関わっていることが明らかになってきました。乱れた腸内細菌を正常化することで、これらの疾患の治療や予防につながる可能性があり、今後の研究にさらに期待が持たれるところです。
2019年2月号

糖尿病で血糖が高いのは良くないこととは聞きますが、逆に良いことはないのでしょうか。

良好なデータを維持できれば、長寿を得られることが期待できます。
内科 医長 保阪 大也
高血糖が体に良いことはありません。脳卒中や心筋梗塞等のあらゆる血管の障害、腎機能障害、免疫力の低下等を起こしますので、良好なコントロールに努めてください。
でも、一病息災という言葉もありますし、少しは良いこともあるかもしれません。
○食事療法の意識:糖尿病食は治療食ではなく、カロリー、塩分を控えたバランスの良い健康食、という考え方です。
○定期的に通院する:体重や血圧を測り、体の状況を話し、記録に残すだけでも健康に対する意識が違ってきます。元の病気とは直接関係のない検査(内視鏡等)も受けやすい環境にあると言えます。健診異常を指摘されながら、受診に一大決心が必要な方も多いのです。
○定期的な採血:何ヶ月かに1回は、肝、腎機能、脂質、貧血等の検査もするでしょう。年に1回健診を受けるかどうかの方に較べれば、異常の早期発見ができる可能性があります。
○併発疾患の治療:例えば糖尿病の方は、高血圧、高脂血症や高尿酸血症等の併発が多く、それによる合併症も無視できません。当然それらの治療も受けられることになります。
○薬の効能:ある種の糖尿病の薬には、降圧効果、脂質や肝腎機能改善効果、心不全予防効果が明らかです。癌の予防効果が期待されている糖尿病薬もあります。血圧の薬にも心臓や腎臓の保護効果があります。
糖尿病は治ることはないにしても、良好なデータを維持できれば、長寿を得られることが期待できるのです。前向きに治療に励みましょう。
2019年1月号

痛風で薬を飲んでいます。1年以上痛み出ていませんが薬を止めていいでしょうか?

医師の指示に従い治療を継続することをお勧めします
整形外科 医長 小川 知周
痛風は尿酸の結晶が関節に貯まり痛みを伴う病気です。以前は男性が80%を占めていましたが最近は女性の患者も増えています。
足の親指に痛みが出ることはよく知られていますが、それ以外に足の甲、足関節、アキレス腱部、膝などにも痛みが出ます。稀ですが手に出る人もいます。
血中の尿酸値が高い状態が続いても痛みはたまにしか出ません。そのため放置している人がたくさんいますが、尿酸は関節だけでなく血管、腎臓などにも貯まり、動脈硬化、腎不全の原因にもなります。また「食事に気をつけてるから大丈夫」と言う人もいますが、最近の研究では食事療法のみで改善する人は1割にも満たないことがわかってきました。
痛みがなくても定期的に血液検査をして医師の指示に従い治療を継続することをお勧めします。
2018年12月号

「30~50代男性の皆さん、風疹ワクチン接種を受けて!」はなぜですか?

過去に男児が風疹ワクチンの対象となっていなかったため、30代後半以上の男性の2割前後が必要な免疫を持っていないためです
小児科 医長 中村 誠
平成30年になって報告された全国の風疹患者数が、10月の時点で1,000人を超えたことが発表されました。昨年1年間(93人)の約12倍に上っており、さらなる流行の拡大が懸念されます。
妊娠20週頃までの女性が風疹ウイルスに感染すると、胎児にも感染して、心臓病や難聴などの障害を持つ先天性風疹症候群の赤ちゃんが生まれる可能性があります。約4万人の流行があった2004年には、10人の先天性風疹症候群が報告されました。
風疹に治療法はなく、ワクチンで感染を防ぐほかありません。男女ともがワクチンを受けて、まず風疹の流行を抑制することが重要です。
中北保健所峡北支所では、妊娠を希望する女性(配偶者、同居者を含む)、抗体価の低い妊婦の配偶者を対象に、無料の抗体(免疫)検査を実施しています。
2018年11月号

なかなか禁煙できず、電子たばこや加熱式たばこに替えてみようかと考えていますがいかがでしょうか。

従来のたばこから電子たばこや加熱式たばこに替えようと思っているということは、禁煙をしようという気持ちがあるのでしょう。 禁煙外来を受診することをお勧めします。
2018年10月号

会社で施行したストレスチェックテストで高ストレス者と判定されました。どのように対応すれば良いですか?(50代男性)

セルフケアを行い、産業医等との面談、上司や同僚と相談(ラインによるケア)してください。
産業医 鈴木 修
ストレスチェック制度は、労働者のストレス状況に関して毎年テストを行い、自己のストレス状況について注意を促すことでメンタルヘルス不調のリスクを軽減させ、また結果を集団的に分析することにより職場環境の改善につなげ生産性を向上させることを目的として、平成27年12月より施行されています。
企業は高いストレスを被っている労働者に対して、自らがストレスへ対処する方法セルフケア)をアドバイスし、産業医等との面談を奨励しなければなりません。産業医は面談によりストレスの原因を検索し、軽減するための就業上措置を企業に提言します。
労働者は、ストレスを蓄積せずメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことが肝要です。
2018年9月号

つらければ使用してもよいし、使用しない選択肢もあります。
小児科 医長 溝呂木 園子
小児の発熱の原因の多くは、感染症と考えられます。ウイルスや細菌が体内に侵入した時には、自らの力で闘うために代謝を活発にし、体温を上昇させて免疫力を高めています。発熱はからだの免疫反応のひとつであるために、無理やり下げる必要はないと考えることができます。一方で、発熱の苦痛や不快が軽減されることは、水分摂取や休息が促されることからもメリットがあります。つまり、発熱時の解熱剤は、つらければ使用してもよいし、使用しない選択肢もあるといえます。ちなみに、熱性けいれんの際には解熱剤を使用しない方がよいといわれてきましたが、最新のガイドラインでは解熱剤の使用がけいれんを誘発する根拠はないとされていますので、熱性けいれんを起こしたことがあるお子さんでも、つらい時には使用してもよいと伝えています。
2018年8月号

高齢の父が食後に座ってテレビを見ていたら、急に顔色が悪くなって意識を失い、寝かせたら数分で元に戻りました。何か脳の病気 が考えられるでしょうか?

一 時的に意識を失ったが短時間で症状を残すことなく回復する発作を「失神」と呼びます。 失神は意識を失うので脳の病気と誤解されやすいですが、循環器 内科でのチェックが必要な場合もあります。
脳神経外科 科部長 八木下 勉
失神は一過性の全脳の血流低下で生じることが多く、最も多いものは神経調節性失神と呼ばれるもので自律神経の調節がうまくいかなくて一時的な血圧低下が生じ、脳の血流が減って失神するものです。血圧が回復して脳血流が戻れば症状はなくなります。食事・飲酒・入浴・排尿便・急な起立などがきっかけになることが多いようです。ただし注意が必要なのは不整脈による失神であり、診断が遅れると生命にかかわることがあり、循環器内科でのチェックが必要になります。失神は意識を失うので脳の病気と誤解されやすいですが、単純な失神であれば頭の検査をする意義は乏しいとされています。「発作の病気」は目撃証言が重要で最大の診断根拠になりますので、発作の状況を正確に医師に伝えることが大切になります。
2018年7月号

大腸癌は今、腹腔鏡手術でできるので手術の後痛くないって本当ですか?

大腸癌は、ほとんどの手術が腹腔鏡下で行うことが可能です。従来の腹腔鏡をつかわない手術に比べると傷自体が小さいので創部痛 みは軽度になります。
外科 医長 赤澤 祥弘
当院で行っている腹腔鏡下の大腸切除ではまず臍に12mmのカメラ用の穴をあけおなかに送気をして膨らませます。その後観察し必要な手術を行ってきます。ただ、腸を切除して取り出す際に臍の近く、もしくは臍の傷を延長して4~5センチほどの傷をつくります。手術のあとに最も傷として痛むのはこの傷かと思います。従来の腹腔鏡を使わない手術に比べると傷自体が小さいので創部痛は軽度になります。腹腔鏡下の手術は以前に比べ手術器具の発達によって大腸癌の他にも胃癌の手術でも行っています。ただ、すべての大腸癌が腹腔鏡手術でできるわけではありません。非常に大きく進行してしまった癌やほかの組織に強く癒着、浸潤しているものは行うことができません。
2018年6月号

骨粗鬆症とはどのような病気ですか? 症状はありますか?

骨の量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。 自覚症状はありませんが、背骨などに骨折を生じるとその部位に 痛みがでます。
整形外科 医長 松木 寛之
日本には1300万人程度の骨粗鬆症の患者さんがいるといわれており、高齢化に伴ってその数は増加傾向にあります。
特に女性では50歳以上の3人に1人が骨粗鬆症といわれており、50歳以上の3人に1人が背骨を、5人に1人が太ももの付け根の骨を生涯のうちに骨折するといわれていて、寝たきりになる原因の一つとなっています。
骨粗鬆症の治療として、薬による治療、食事療法、運動療法が挙げられますが、一旦骨が弱くなりすぎてしまうと再び骨を強くするのは難しくなりますので、50歳以上の方で今まで検査を受けたことがない方は整形外科などを受診して骨密度検査を受けてください。
2018年5月号

「腸内フローラ」という言葉をよく耳にしますが、「腸内フローラ」とは何ですか?

腸内の壁面に生息している多様な腸内細菌が種類毎にまとまっている様子が、あたかも種々の植物が種ごとに群生しているお花畑 (flora)のようであることから、「腸内フローラ」と呼んでいます。
内科 副院長 三澤 明彦
私達人間の腸内には多くの細菌が生息しており、これを腸内細菌と言い、実に数は約100兆個あると言われています。
腸内細菌は、悪玉菌の侵入や増殖を防いだり、腸の運動を促したり、人の体に有用な働きをする善玉菌(ビフィズス菌や乳酸菌など)と、腸内の中を腐らせたり、有毒物質を作る悪玉菌(クロストリジウムやブドウ球菌など)と、善玉とも悪玉とも言えず、体調が崩れたときに悪玉として働く日和見菌(大腸菌やバクテロイデスなど)に大別されます。
何らかの原因(食生活や生活習慣、薬(抗生物質など))で腸内フローラのバランスが崩れると、悪玉菌は増え、便秘や下痢などのお腹の調子を悪くするだけでなく、様々な生活習慣病や肌荒れ、肩こり、老化などにも関係すると言われています。
昨今腸内フローラは、肥満やがんや糖尿病やアレルギーや認知症との関連も注目され、一部の疾患に糞便移植療法などの効果が示され、今後の研究に期待がよせられています。
2018年4月号

マイコプラズマ肺炎はどんな病気ですか。

感染者との食事や車の同乗などの濃厚接触によって感染するとされています。発熱、頭痛、だるさが最初の症状で、その後徐々に咳 が強くなり、解熱後も長く続く傾向があります。
小児科 医長 中村 誠
晩秋から早春にかけての発症が多く、罹患年齢は幼児期、学童期、青年期が中心となっています。
感染には、向かい合っての食事や車の同乗など濃厚接触が重要とされており、学校などでの短時間の暴露による感染拡大はあまりみられません。感染を受けてから症状出現までの潜伏期は通常2~3週間で、発熱、頭痛、だるさなどが最初の症状です。咳はその3~5日後から始まることが多く、経過に従い徐々に強くなり、解熱後も長く続く傾向があります。胸部レントゲン検査に加え、喉のぬぐい液や血液の検査で診断が確定されます。
抗菌薬による化学療法が治療の基本となるため、病院受診をお勧めいたします。特別な予防法はありませんが、マスク着用、手洗い、うがいなどの一般的な予防法と、咳や熱のある方との濃厚な接触を避けることが重要です。
2018年3月号

インフルエンザと診断され、抗ウイルス薬を処方されましたが、3日経っても熱が下がりません。

インフルエンザ以外の病気や、インフルエンザ後の二次感染の可能性があります。医療機関を受診しましょう。
内科 医長 池田 フミ
インフルエンザの診断は難しいのです。ウイルス迅速検査は突然の発熱から12時間から24時間で陽性率が高いと言われています。検査のタイミングでは陽性にならない場合もあります。また高齢者では37度台の微熱のこともあります。高熱でないから/検査で陰性だからインフルエンザではない、とは言えないのです。発熱してから48時間以内であれば抗ウイルス薬の効果が期待できるため、総合的に診断し、適切な治療が必要となります。
しかし3日経っても熱が下がらない、咳や痰が多くなったり、下痢をしたり、食事が食べられない、頭痛がひどいなどの症状が続くときは、インフルエンザではなく、違う病気かもしれません。インフルエンザ以外のウイルス感染では熱は2週間近く続くこともあります。発熱の原因が細菌感染の場合はウイルス感染とは違い、適切な抗生物質の治療が必要です。インフルエンザに罹った後の二次感染(細菌感染)は高齢者や免疫力が低下している患者さんには特に注意が必要です。
3日経っても熱が下がらない場合は医療機関を受診しましょう。
2018年2月号

最近寒くなり明け方によくふくらはぎがつります。何か病気でしょうか?

汗のかきすぎ・水分の摂り過ぎや、血行不良などが原因として挙げられますが、毎日のようにつる方は特定の病気による可能性があ るので、病院への受診をおすすめします。
整形外科 医長 小川 知周
つることはこむら返りと言いますが、これは筋肉の異常な収縮で起こります。その原因として、①電解質のバランスが崩れる ②血行不良 ③特定の病気 があります。
夏場に激しく汗をかいたり、逆に水分を採りすぎると電解質のバランスが悪くなります。
寒い時期は血行が悪くなることでつることが多くなります。
特定の病気とは糖尿病、肝硬変、腎不全、甲状腺機能低下症、動脈硬化や神経系の障害などです。
妊娠中の方も起こりやすいです。
予防としては血行不良を改善させるビタミンEや筋肉の弛緩作用があるマグネシウムの摂取、適度な運動、睡眠不足の解消などです。特定の病気がある方はその病気の治療をしなければ改善しないので、毎日のようにつる方は病院への受診をおすすめします。
2018年1月号

熱性けいれんはどんな病気ですか?

かぜなどの発熱に伴って起こるけいれんです。 体を反らせたり手足をがくがくさせたりしますが、心臓が止まる ことはありませんので、落ち着いて安全な所に寝かせてください。
小児科 溝呂木 園子
熱性けいれんは、かぜなどの発熱に伴ってけいれんを起こす状態で、小児の脳が熱に対して敏感であるためといわれています。熱の上がり際に多く、突然呼びかけに反応がなくなり、身体を反らせて硬くなったり、手足をがくがくさせる状態になります。顔色が悪くなることもあります。
とても驚きますが、心臓が止まることはありませんので、まずは落ち着いて、安全な所に寝かせてください。服は緩めて呼吸をしやすいようにします。嘔吐することがあるので、窒息しないように顔は横向きにします。多くは5分以内に止まり、いったん意識が戻ってから眠ります。
発熱を伴うけいれんの中でも、「10分以上続くけいれん」「初めてのけいれん」「乳児のけいれん」「意識障害が続いている場合」等は、熱性けいれんではない可能性がありますので、早期の受診が必要です。
2017年12月号

今度手術を受けることになりましたが、内視鏡手術も行われていると聞きました。どのような手術ですか?

体に小さな穴をいくつか開けてカメラを挿入して行う手術です。傷が小さいため見た目が綺麗で、痛みが少なく術後の回復が早いこ とが特徴です。
外科 齊藤 亮
内視鏡手術とは、体に小さな穴をいくつか開けてカメラを挿入して行う手術です。現在では様々な病気に対して、広く安全に行われています。例えば、当院では胆嚢(結石やポリープ)、鼠径ヘルニア、大腸癌、胃癌、虫垂炎、気胸などに対して内視鏡手術を行なっています。
メリットとして、傷が小さいため見た目が綺麗で、痛みが少なく術後の回復が早いことなどが挙げられます。早期の社会復帰も可能となります。癌に対する治療成績(癌の治り具合、再発の程度や合併症の少なさなど)は、開腹手術に劣らないことが示されています。一方、過去に開腹手術を受けたことがある人や、全身状態や病気の種類によっては内視鏡手術よりも開腹手術の方が望ましいこともあります。
どちらの方法が良いか、治療方針を決める際に主治医の先生と相談してみるといいでしょう。
2017年11月号

骨密度が低くなければ骨折する心配はないのでしょうか?

骨密度が高くても弱い骨も存在します。骨を健康に保つには、食生活や生活習慣を改善する一次予防が大切です。
整形外科 医長 小林 憶人
骨の強さは骨密度だけでは表せません。骨にはそれぞれ質があり、密度が高くてもガラスの様に弱い骨も存在しています。
最近の研究により、骨の質が弱くなる要因にはカルシウムなどの栄養素が不足する他、喫煙、過度の飲酒、運動不足などにより動脈硬化や糖尿病といった生活習慣病を引き起こすことで骨が弱くなることが指摘されています。骨を健康に保つためには、食生活や生活習慣の改善といった一次予防が大切です。また、骨粗鬆症は生命予後にも影響することが知られており、骨折の二次予防として、定期的に骨の健康診断を受け、骨粗鬆症を早期に発見することで、早期治療を開始することができます。
もし骨折をしてしまった場合には、次の骨折を事前に防ぐ三次予防として積極的な治療を開始しましょう。骨折を事前に防ぐことで健康寿命を延伸することができます。
2017年10月号

C型肝炎ウイルスを治療して、ウイルスが消えたと言われました。これでもう肝臓癌にもならないのでしょうか?

C型肝炎ウイルスを治療した後も、その後に肝細胞癌になってしまう方は少なくありません。肝癌早期発見のため、定期通院を続け た方が望ましいです。
外科 医長 平井 優
C型肝炎のウイルス治療に関しては、以前からインターフェロン療法が行われていましたが、患者さんによっては、強い副作用を起こす方や、なかなかウイルスを排除出来ない方もいて治療が難しいと言われていました。
ところが最近ではDAA製剤と言われるC型肝炎ウイルスを治療する飲み薬が開発され、副作用も少なく、100%に近くウイルスを排除することができます。
肝細胞癌の原因の約70%がC型肝炎と言われています。しかし、残念ながらせっかくC型肝炎ウイルスを排除しても、その後に肝細胞癌になってしまう方は少なくありません。ただし、ウイルス排除によりC型肝炎がこれ以上悪くならないので肝機能が保たれ、たとえ発癌しても手術やカテーテル治療などの治療の選択肢が広がり結果的に生存率の改善につながります。C型肝炎ウイルスを治療した後も、肝癌早期発見のため定期通院を続けた方が望ましいと考えます。
2017年9月号

糖尿病患者数が増えているそうですが、どのような状況ですか?

日本だけでなく世界でも年々増加していて、70歳以上の日本人の男性の4人に1人・女性の6人に1人が糖尿病患者とみられ、過去最 高の状況です。
内科 医長 保阪 大也
厚生労働省の調査によると、平成26年の糖尿病患者数は316万6000人(前回平成23年調査で270万人)で、過去最高でした。年齢と共に増加し、70歳以上になると男性の4人に1人、女性の6人に1人が糖尿病とみられます。
平成28年に甲府市が無料簡易検査をしたところ、240人が検査を受け、そのうち半数以上が糖尿病の疑いがあるとの結果でした。山梨県は健康寿命が長い、と言われていますが、糖尿病による死亡率はワースト8位です。
糖尿病は世界的にも増加傾向にあり、何らかの策を講じないと、医療費だけでも大変なことになることが懸念されています(平成27年時 4億1500万人、成人の11人に1人)。
世の中はまだまだグルメや大盛りがブームであり、食事制限を勧めることは景気対策にも水を差しますが、健康に良くない面もかなりありそうです。
糖尿病食は病人食ではなく健康食、と考え、糖尿病の方もそうでない方も、一度勉強してみることをお勧め致します。
2017年8月号

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)が心配なので、食べ物でカルシウムを多めにとっていますが、それでよいでしょうか?

それでは不十分です。整形外科を受診し骨密度検査や血液検査をして、適切な治療薬をみつけましょう。
整形外科 科部長 神平雅司
骨粗鬆症は、骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気ですが、カルシウム不足だけが原因ではありません。
骨は、一生の間に繰り返し作り替えられています。それには古くなった部分を解体する細胞と、そこに新しい骨を作る細胞が協力しあっています。この解体する細胞の働きが活発になり過ぎた状態が骨粗鬆症です。
現在の骨粗鬆症の治療薬は、解体する細胞の働きをおさえるものが一般的です。それには内服薬(毎日、週に1度、月に1度)、注射薬(月に1度、半年に1度、年に1度)があります。また、1年半から2年間の限定で新しい骨を強力に作る薬もあります(毎日自分で注射、週に1度医療機関で注射)。
自分に最もあった治療薬をみつけるには、整形外科を受診し骨密度や血液検査をして決めてもらいましょう。
2017年7月号

60歳代女性。検診で胆嚢に径12mmのポリープを指摘され、症状はありませんが、胆嚢を摘出する手術を勧められました。 どのような病気なのでしょうか?

胆嚢の内面に形成される、ほとんどはコレステロールが沈着した良性のポリープですが、まれに悪性(胆嚢癌)の危険性があります。
外科 副院長 鈴木 修
胆嚢ポリープは、胆嚢の内面に形成される限局した隆起病変で、5~10%程度と比較的多くの方に認められます。ほとんどはコレステロールが沈着した良性ポリープですが、稀に悪性(胆嚢癌)の危険性があります。
腫瘍マーカー等の血液検査、エコー、CT、MRIなどにより良性と悪性の鑑別を行いますが、胃や大腸のポリープと異なり内視鏡で組織を採取することが不可能なため、確実な鑑別が困難な場合も存在します。直径が10mm以上、短期間に増大傾向を示す、広い茎を有する等のポリープは、悪性の危険性が存在し、診断と治療のため胆嚢を摘出することが望まれます。
摘出術として、腹部に3~4箇所の穴を開け腹腔鏡を用いた手術を行います。ポリープが肝臓や胆管などの周囲に浸潤している場合や、病理検査にて再発の危険性が高いと考えられる際には、肝臓・胆管・リンパ節の切除を追加します。
2017年6月号

叔父が脳出血と診断されて入院中です。片麻痺があるそうですが、手術はしなくても良いのでしょうか?

最近では、手術による改善効果は限られている、というのが通説で、手術の対象とされる患者さんは少なくなっています。
脳神経外科 科部長 八木下 勉
以前は、ある程度の大きさの脳出血なら積極的に開頭手術で取り除くことが行われたこともありますが、最近では、手術による機能予後の改善効果(手術をしたらどれだけ症状が良くなるか)はかなり限定的である、というのが通説となり、手術の対象とされる患者さんは少なくなっています。手術の適応となるのは、
①出血がそれなりに大きくて、②脳の表面近くにある場合、または③小脳出血である場合、④症状が重篤で救命を目的とする場合
などです。ただし、最後④の場合は救命できても重い後遺症が残ります。脳出血はその部分の脳がすでに「破壊されて」いますので、手術をしても症状は改善しにくいといえます。
手術の方法は従来からの開頭手術のほか、最近では定位的血種除去や内視鏡を使った方法など、病状に応じて使い分けられています。また、若い人や血圧が高くない人の脳出血では、その裏に出血を起こす別の病気が隠れていることがありますので、精密検査をしてそのようなものが見つかれば、それに対して手術や放射線治療を行うことがあります。
2017年5月号

心窩部痛や胃もたれ感があり、病院で検査を受けたのですが、異常が見つからず、機能性ディスペプシアと言われました。 どんな病気ですか?

症状の原因となりそうな「器質的」な疾患が認めらないにもかかわらず、胃もたれや心窩部痛などの症状が現れる「機能性」の疾患 です。
内科 副院長 三澤 明彦
機能性ディスペプシア(FD:Functional Dyspepsia)とは、上部消化管に消化性潰瘍や癌などの器質的疾患が認められないにもかかわらず、胃もたれや心窩部痛などのつらい症状が現れる機能性疾患です。診断基準は、
- A. つらいと感じる食後のもたれ感、
- B. 早期飽満感、
- C. 心窩部痛、
- D. 心窩部灼熱感
のうちの症状が1つ以上3か月以上続き、かつ、症状の原因となりそうな器質的疾患(上部内視鏡検査を含む)が確認されないことです。
症状発現のメカニズムは未だ不明な点が多いものの、胃運動機能異常、生活習慣、ストレス、内臓知覚過敏、胃酸などが複雑に影響し合っているものと考えられています。
治療は、機能性なので気のせい?と済まされてしまう事もありますが、ストレスを回避するような生活習慣の改善や、食生活の改善も重要ですが、それぞれの症状に応じて消化管運動機能改善薬や酸分泌抑制薬、防御因子増強薬、制酸薬、漢方薬や時には抗うつ薬や抗不安薬が処方される事もあります。
2017年4月号

学校検尿で血尿と蛋白尿が両方陽性でしたが、どうすればいいですか?

腎炎の可能性があります。まずは受診をしてみて下さい。
小児科 院長 東田 耕輔
血尿と蛋白尿がともに陽性だとすれば、腎炎の可能性が高いと考えられます。
腎炎の中には、急速に悪化して数か月で慢性透析まで進行してしまうものや、徐々に進行して10-数十年後に慢性透析になる疾患が含まれています。20年程前までは、治療法がなかったのですが、この数年は開発が進み、最も患者さんが多いIgA腎症は、出来るだけ早期に診察を受け、必要な場合、検査・入院治療を行えば、多くの場合、血尿や蛋白尿も消失して透析へ進行するのを阻止できるようになって来ました。
韮崎市は、甲府市に続き、昨年度から、県下で2番目に新たな学校検尿システムが導入されており、学校検尿登録医を受診すれば、腎炎の発見に必要充分な検査が行われ、必要な場合は大学病院等に紹介されるシステムが出来上がっています。早く、受診しましょう!登録医が分からない場合は、学校にお問い合わせください。
受付時間 |
再診 8:00~(再来受付機) 初診 8:30~11:30 小児科の午後の診療は予約制です 泌尿器科は事前予約必須です 下記診療科の午前の受付は11時までになります。 ・外科 そのほか診療科によって異なる場合があります。 詳細は外来担当表でご確認ください。 |
診療時間 |
9:00~17:15 |
休診日 |
土・日・祝日 年末年始 |
入院患者面会時間 |
面会禁止 (手術説明や病状報告を除く) |

上記キャッシュレスサービスが利用できます
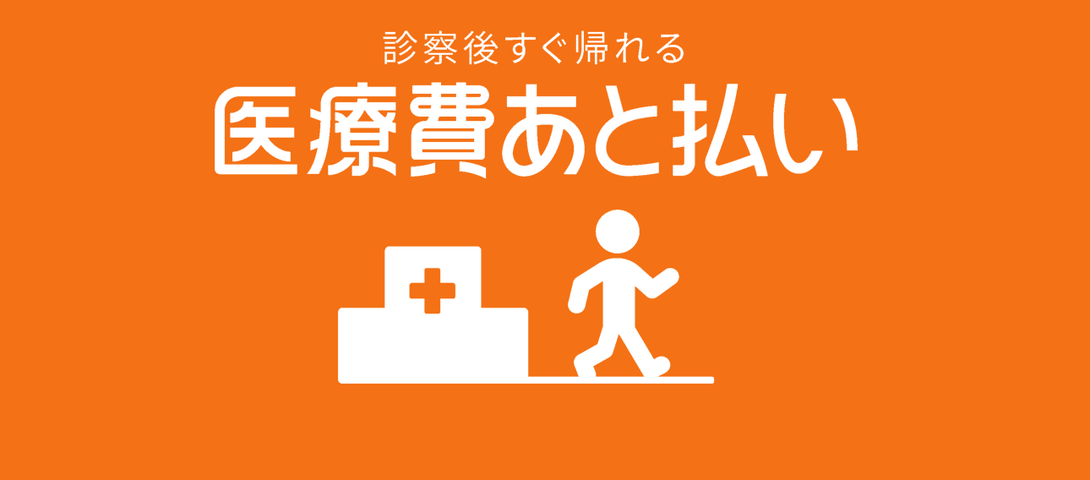
ご利用できます。
あと払い会員ページ ログインはこちらから